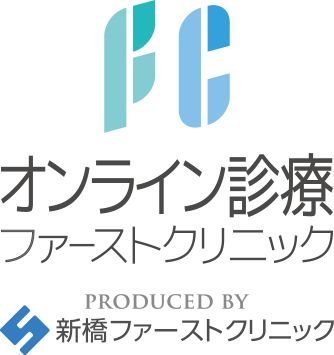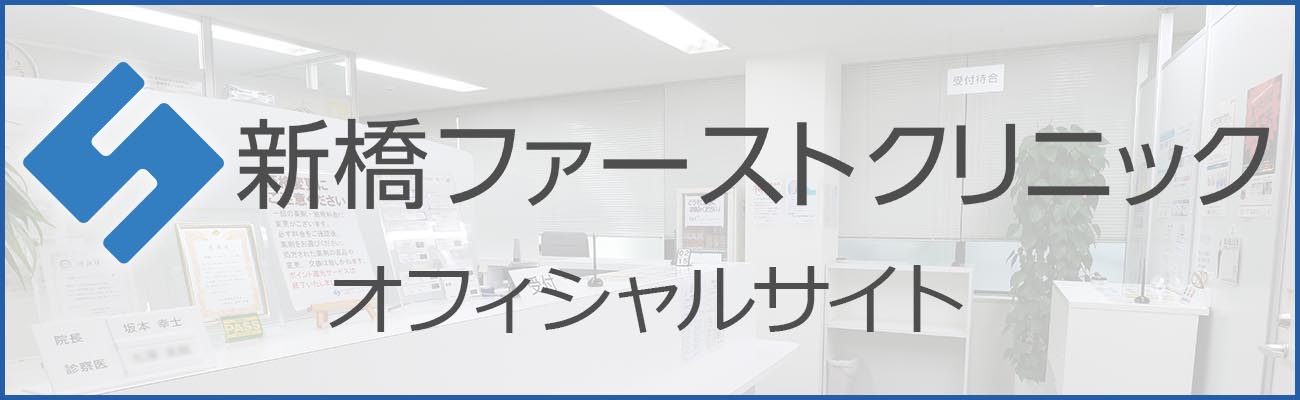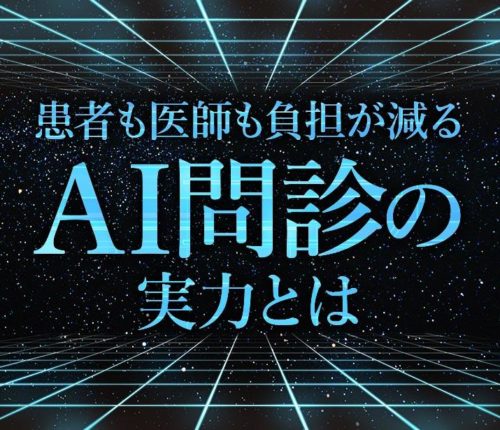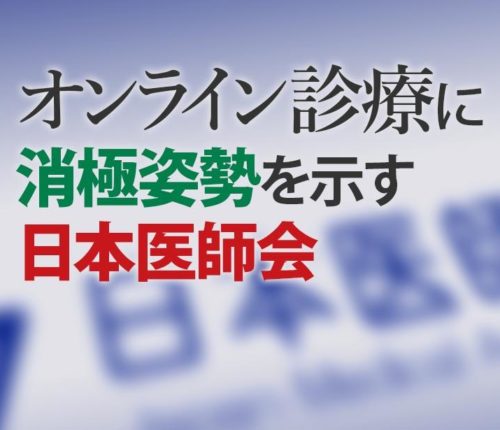- 2025/12/03:クリニクスによるオンライン診療は終了いたしました
- 2025/02/12:LINEでオンライン診療を受けられるようになりました(詳しくはこちら)

Telemedicine Report
記事リリース日:2018年11月19日 / 最終更新日:2019年1月21日
オンライン診療(遠隔診療)は
被災地支援にマッチする

地震や台風の被災地では普段より多くの医療が必要になるのに、医療が壊れるという、二重苦に襲われます。
住民たちは、最も医療を必要とするタイミングで、“近くの医療”を失う状況に恐怖すら感じるでしょう。
また医師や看護師たち医療従事者も被災者になり得ます。
医師が被災すると、治療を提供できないどころか、自身が治療を受けなければならないのです。
被災地の医療支援では、オンライン診療(遠隔診療)が力を発揮しそうです。
現在はまだ、地震が起きたらすぐにオンライン診療を拡大する体制は整っていませんが、ある企業が主導してそれに近い形を提案し注目を集めています。
目次
被災地がどれほど医療を必要とするか

オンライン診療(遠隔診療)が被災地医療を支援することの意義を実感するには、被災地がどれほど医療を必要とするのかを知っておいたほうがいいでしょう。
2011年3月11日に発生した東日本大震災では、発生直後から全国の医師や看護師たちが医療支援のため現地入りしました。
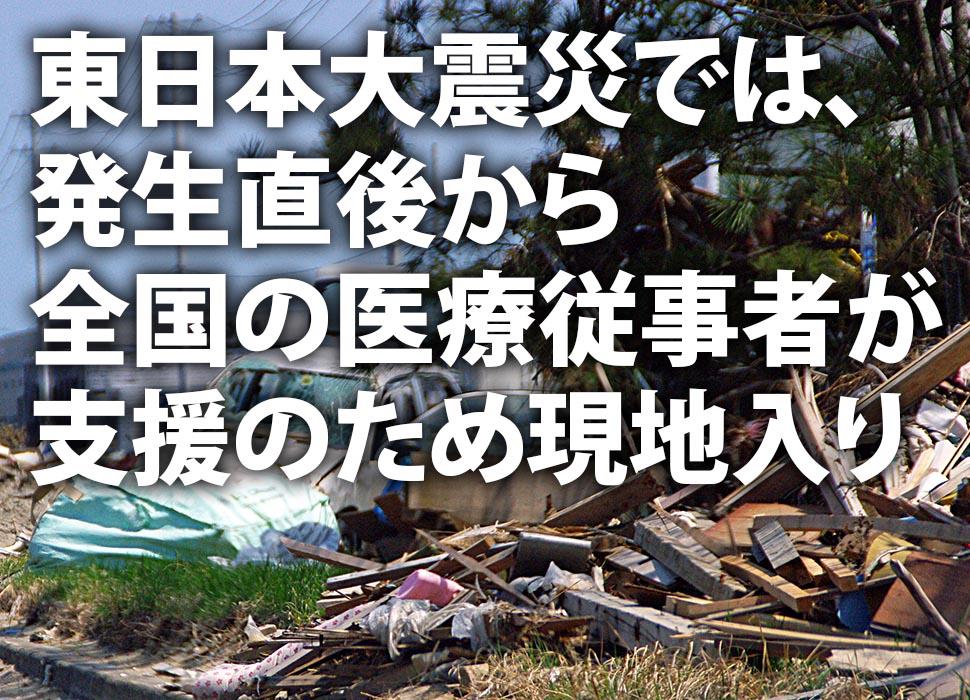
東日本大震災は1,000年に一度と言われている程の巨大な津波に襲われたため、亡くなった方の9割は溺死でした。
つまり地震や津波によって大けがを負って治療が必要になった方は、“比較的”少なかったのです。
すぐに現地にかけつけた東京の大学の医学部准教授は「死体ばかりで、助けられる傷病者は少なかった」と証言しています。
では“比較的”多かった患者はというと、慢性期や亜急性期の“震災前からの患者”たちでした。
そして震災前の患者たちを救うことは、次の理由から困難を究めました。
- ・薬が流されたのに新しい薬が届かない
- ・病状が悪化してさらに充実した医療が必要になった
- ・寒さと食料不足、避難生活のストレスで被災前に病気にかかっていなかった人も病気になりやすかった
- ・衛生状態の悪化によるウイルス性腸炎が発生した
- ・粉塵による上気道炎が発生した
ここからわかることは、被災地に最も必要な医療とは“普通の医療”なのです。
東日本大震災発生直後からしばらくは、大学病院の高度医療や最先端医療ではなく、どこの街にでもある一般的なクリニックの医療が大量に必要だったのです。
被災地の医療がどれほど崩壊するか

次に、2018年9月6日発生した北海道胆振東部地震において、医療がどれほど崩壊するのか紹介します。
この地震による被害で全国的に注目されたのは、停電でした。
震源地近くに北海道内のすべての電力に影響を及ぼす北海道電力苫東厚真火力発電所があり、そこが大打撃を受け北海道内すべてが停電したのです。
日本医師会幹部は地震から約1週間後に、停電が被災地医療に与える影響は大きいと指摘しました。
電気が使えなければ現代の医療の多くは動きませんので、停電が被災地医療に影響を与えるのは当然のような気がします。
しかし、日本医師会幹部が指摘したのは、病院の自家発電装置用の燃料の備蓄量についてでした。
北海道の面積は九州の約2倍もあります。
それだけ広大な土地のすべての電気が止まったので、燃料を買い求める人が急増しました。
エネルギー需要が逼迫(ひっぱく)したことで、被災地の病院は自家発電装置用の燃料確保に奔走(ほんそう)することになったのです。
ポケットドクターの試みとは

それでは、オンライン診療(遠隔診療)と被災地医療の関係についてみていくことにしましょう。
オンライン診療システム「ポケットドクター」を開発・提供している株式会社オプティム(本社、東京)などが、2018年北海道胆振東部地震の被災地支援として、ボランティア医師によるオンライン健康相談を無償で実施しました。
わずか4日で支援態勢を構築
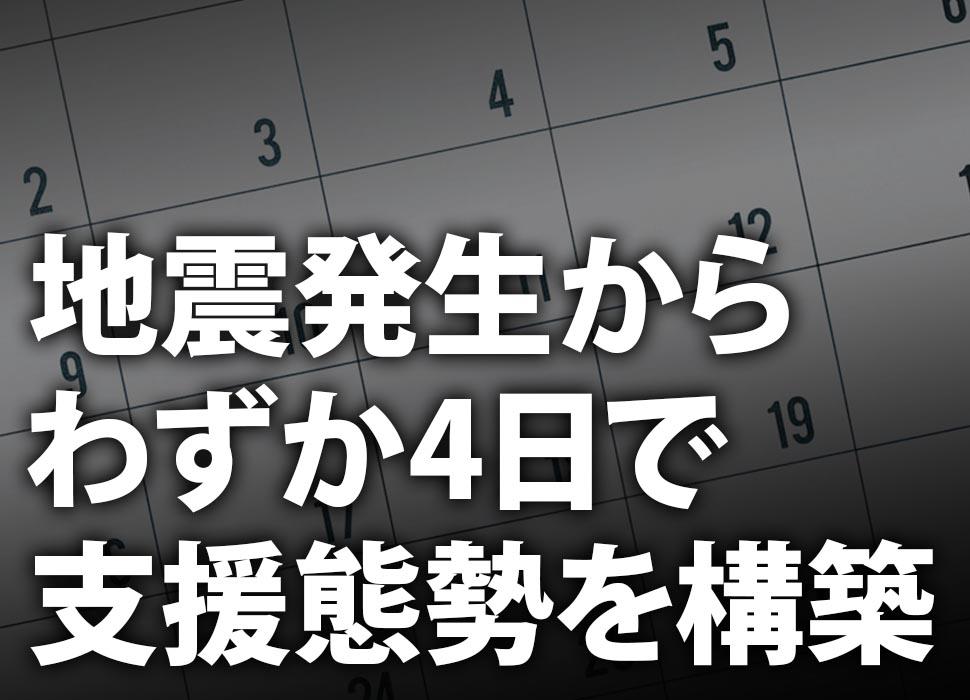
オンライン健康相談の実施期間は9月11日から10月31日までの約1カ月半です。
オプティムなどがこの取り組みを公表したのが9月10日ですので地震発生(9月6日)からわずか4日でサポート体制を整えたことになります。
これはIT技術をふんだんに使っているオンライン診療ならではのスピード感といえるでしょう。
IT技術自体が時間短縮性や効率性を持ちますが、それよりもオンライン診療を実施している医師はITを使い慣れているので、通信機器をフル稼働させて俊敏に行動することができたのでしょう。
従来のオンライン健康相談サービスを応用
被災地向けオンライン健康相談の支援内容は、ボランティア医師たちが、被災地の患者に無償で健康相談にのることです。
オプティムなどは今回の地震とは関係なく、「健康相談ポケットドクター」というサービスを提供していました。
これは、心身に不調はあるが病院やクリニックに行くほどではないと感じている人の健康相談に、医師がインターネット経由で回答するというものです。
健康相談は医師が行っていますが、病気を確定する診断も処方箋の発行も行っていません。
つまり保険医療による行為ではないのです。
今回の地震被災地支援で導入したオンライン健康相談は、この健康相談ポケットドクターを応用したものです。
平日の12時間対応
地震被災地向けの無償のオンライン健康相談を受けることができる時間帯は、土日と祝日を除く9時から21時までの12時間です。
1つのアカウント(スマホ1台)で月3回まで相談できます。
これだけの長時間、ボランティア医師たちが対応できるのは、オンライン診療だからでしょう。
対面方式の健康相談でれば、患者を迎え入れたり待たせたりしなければなりませんが、オンライン診療であれば、ボランティア医師たちの空き時間に対応することができます。
オンライン診療ならテレビ会議やスカイプの要領で、双方にとって都合の良い時間に双方にとって都合の良い場所で開始でき、事前の準備も事後の後片付けも不要です。
極論すれば、医師の仕事は“オンライン診療が患者とつながっているときだけ”で済むのです。
しかも他のスタッフの手をわずらわせることもありません。
オンライン診療は被災地をどう支援するのか
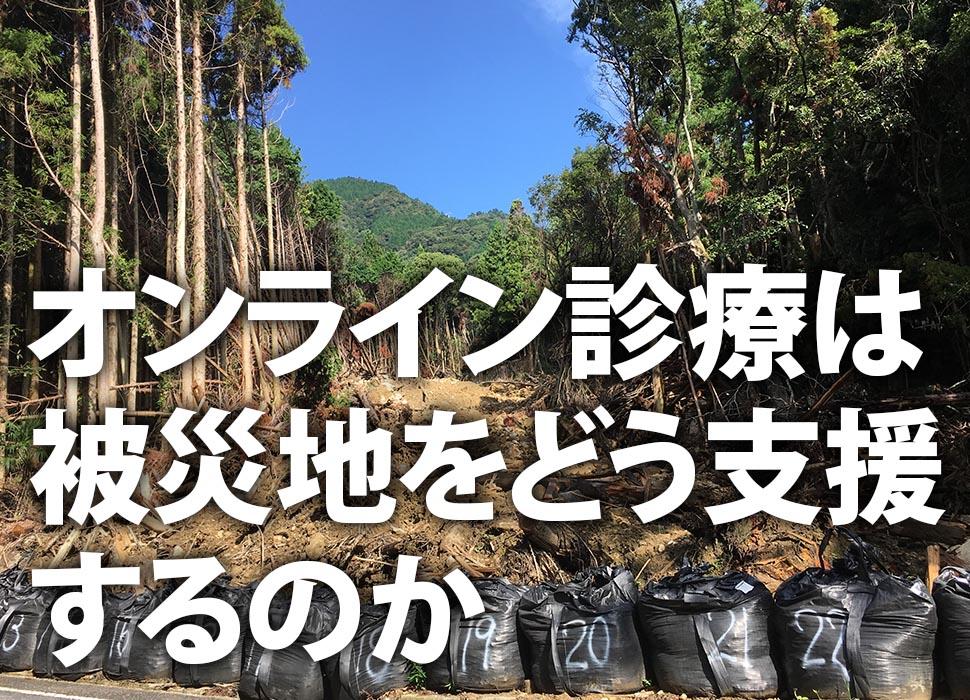
オンライン診療(遠隔診療)を使った被災地支援のメリットは、まさに“医師が遠隔地にいること”です。
オンライン診療を行う医師は、安全な場所から被災地の患者を診ることができます。
もちろん、現地に向かうボランティア医師も重要です。
しかし、現地のボランティア医師は対応に忙殺されるはずです。
そのようなとき、軽傷や慢性疾患の患者の対応をオンライン診療医師が担当すれば、現地の医師たちの負担が相当減り、より重篤な患者の治療に専念することができます。
また、オンライン診療があれば、慢性疾患の患者による受診抑制も防げるかもしれません。
慢性疾患の患者は、病院が患者でごった返している様子をみたら、いつもの薬をもらう事を躊躇ってしまうかもしれません。
しかしそれでは症状が悪化してしまいます。
オンライン診療なら、遠慮がちな慢性疾患患者も気兼ねなく治療を継続することができますし、オンライン診療であれば患者が病院に行く必要がないので、病院に負担がかかりません。
まとめ~“自然災害大国”に必要な医療ツール
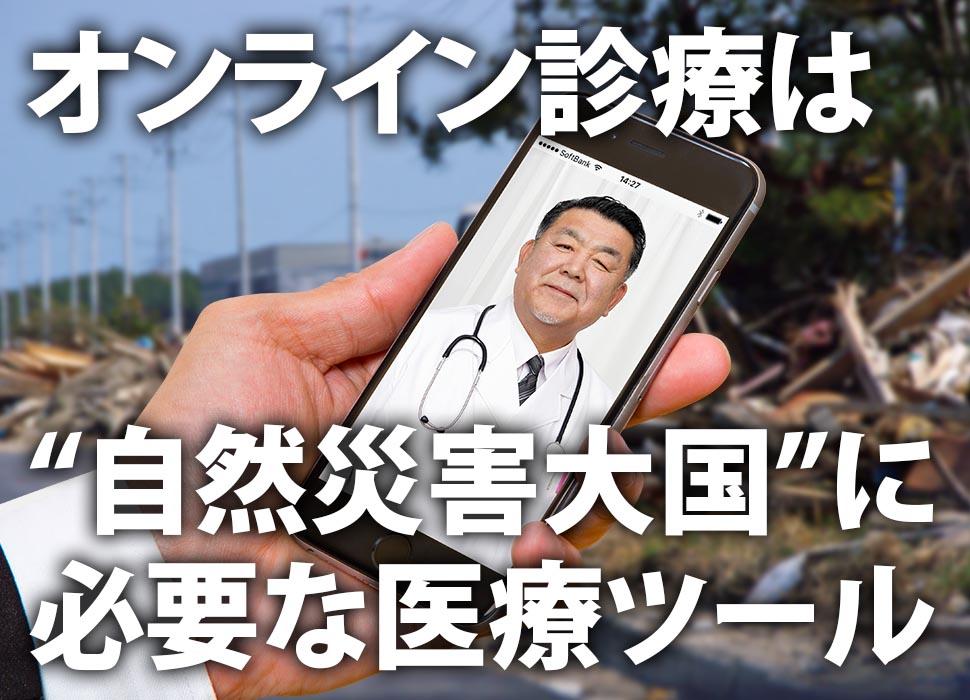
北海道の地震におけるオンライン診療(遠隔診療)の活用は、“試み”でした。
しかし、最早“自然災害大国”の様相を呈しきた日本では、今回の取り組みをもっと広げていったほうがいいのではないでしょうか。
オンライン診療は、被災地の住民が求める“普通の医療”や“日常の医療”をこれほど効率よく提供できる手段なのですから。
料金設定も「予約料500円+お薬の送料一律500円+お薬代」のみとなっております。
厚生労働省の告知に基づき、当クリニックでの初診は来院で受診して頂いた上で、
再診時よりオンライン診療による受診が可能となります。
この記事を読んだ方は他にこんな記事も読んでいます
-
患者も医師も負担が減るAI問診の実力とは
2019年3月8日
「医療の効率化は、患者にも医師にもメリットをもたらし、医療費の削減につながる」 このようなことがよくいわれます。 医療の効率化の重要性は、国民も医療機関も厚生労働省も認識しています。 ...
詳しく見る >
-
オンライン診療に消極姿勢を示す日本医師会
2018年8月17日
日本医師会(日医)の副会長が2018年6月、公の場で「オンライン診療(遠隔診療)はあくまで対面診療の補完」「初診でのオンライン診療は認めない」と強調しました。 同年4月にオンライン診療は医療...
詳しく見る >
-
政府の「未来投資会議」がオンライン診療に注目する理由
2018年7月30日
オンライン診療(遠隔診療)が大きな政治課題になっていることをご存知でしたか。日本政府には「未来投資会議」という総理大臣やネット企業の代表や大学の代表たちが集まる場所があるのですが、そこで医療改...
詳しく見る >
-
オンライン診療(遠隔診療)のメリットとデメリット【2019年版】
2017年11月10日
自宅や職場に居ながらスマホやパソコンのテレビ電話で医師の診療を受ける――。 そんな未来の医療がとうとう現実のものとなりました。 インターネットを使った遠隔医療の仕組み...
詳しく見る >
-
オンライン診療(遠隔診療)とIoTの関わり
2018年1月4日
オンライン診療(遠隔診療)にIoTは欠かせません。IoTが存在していたからこそ、診療行為が遠隔化できるようになったのです。そういった意味では、IoTはオンライン診療の“生み”の親です。そしてI...
詳しく見る >
-
厚生労働省が推し進めるオンライン診療(遠隔診療)とは
2017年10月2日
オンライン診療(遠隔診療)は、これまでの日本の医療をさらに前進させる力を持っています。しかし、あまりに新しすぎて、国は当初、慎重姿勢でした。もちろん、人の命に関わる政策なので、厚生労働省のこと...
詳しく見る >