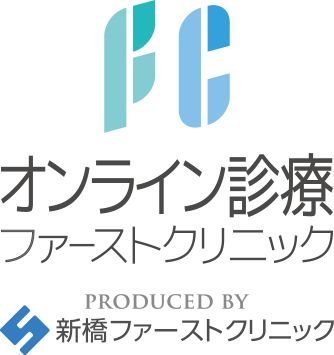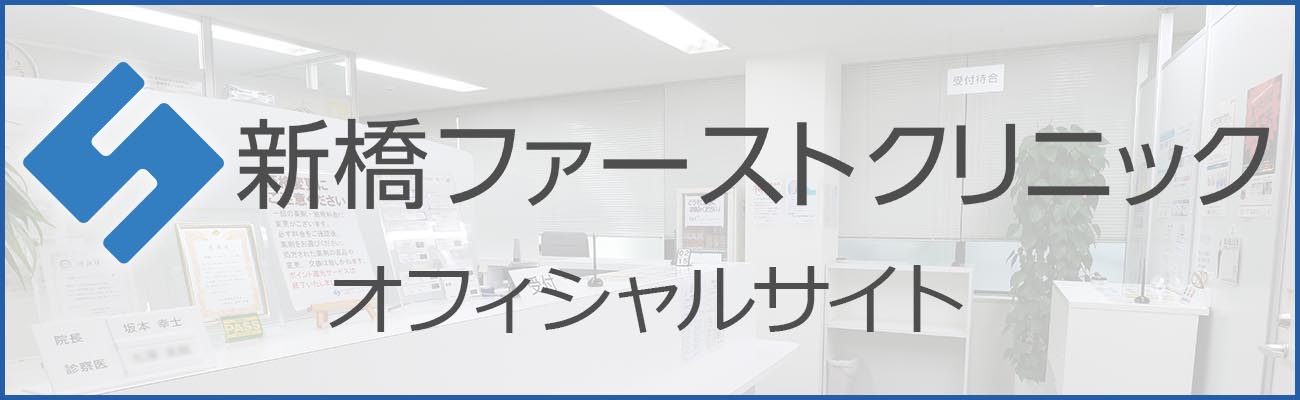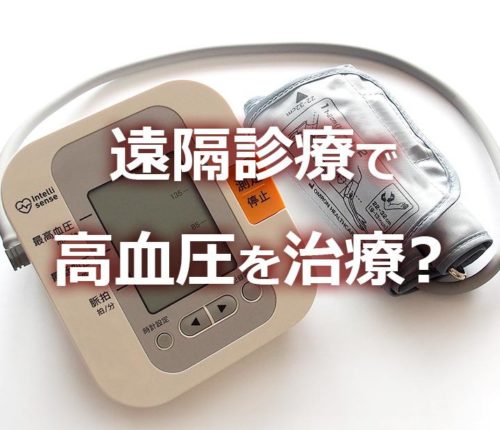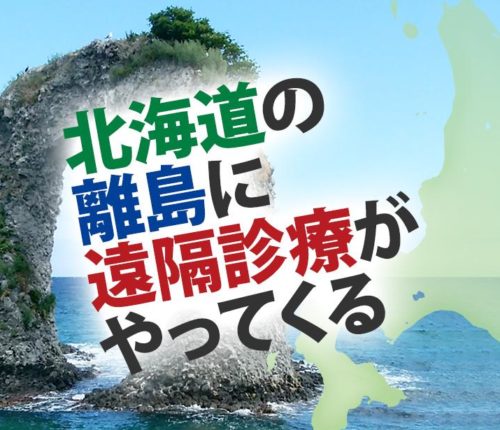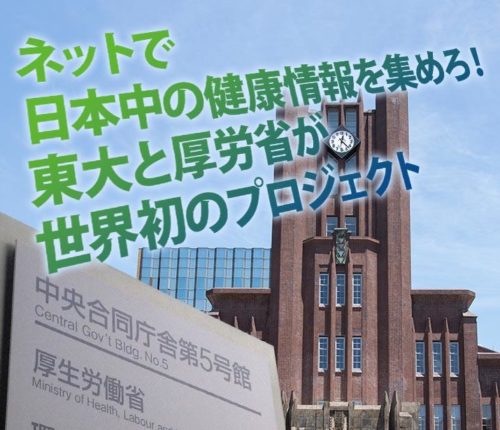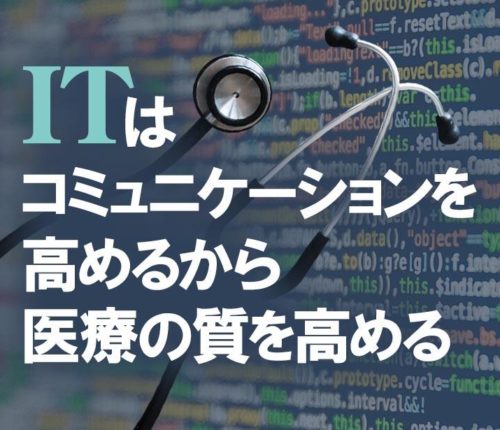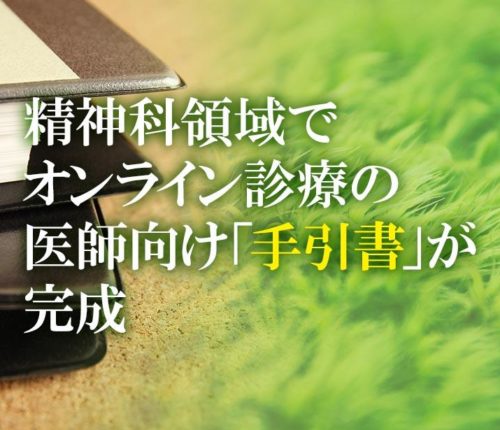Telemedicine Report
記事リリース日:2019年4月9日 / 最終更新日:2019年4月9日
オンライン診療は「こう変わる」
厚労省が見直しに着手
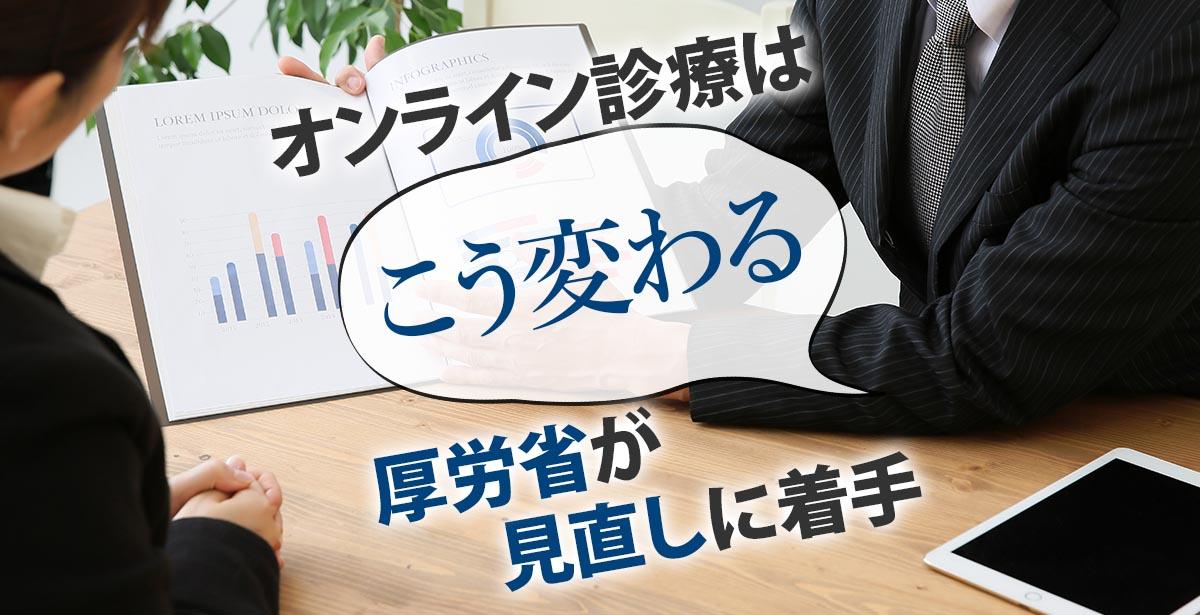
厚生労働省が2019年1月、オンライン診療(遠隔診療)の在り方を見直す作業に入りました。
オンライン診療は2018年4月に公的医療保険の対象になり本格的にスタートしましたが、依然として規制が強く「使いにくい」と感じている医師や患者は少なくありませんでした。
厚生労働省は「オンライン診療の見直し検討会」を設置し7つの改善ポイントを提示しました。
これで医療機関と患者に歓迎される仕組みに生まれ変わることができるのでしょうか。
目次
「オンライン診療の見直し検討会」とは
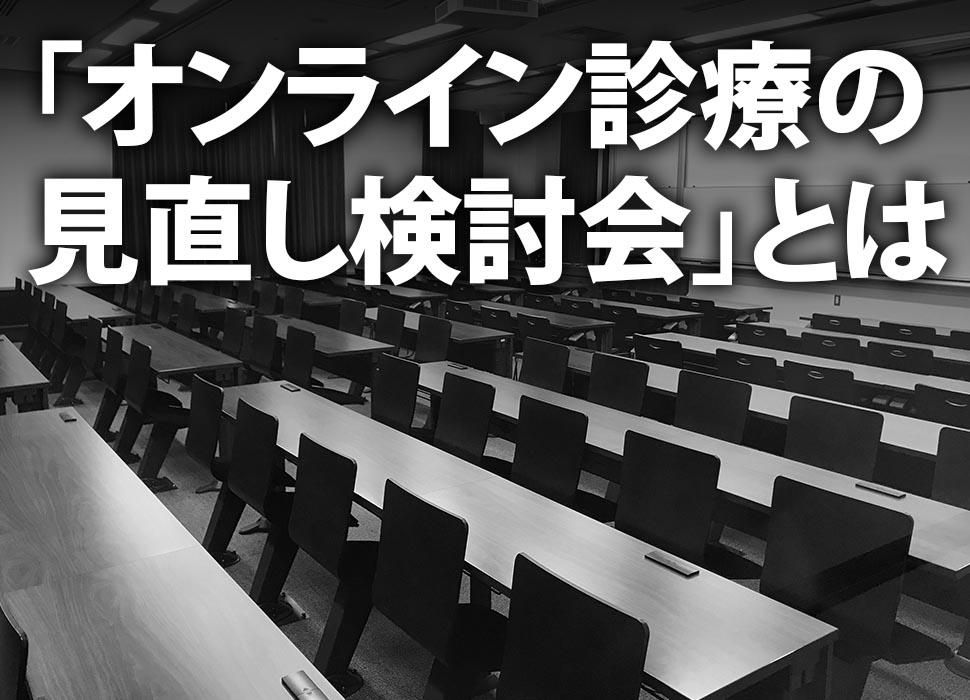
オンライン診療の見直し検討会の正式名称は「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」といい、その初会合が2019年1月23日に都内で開かれました。
出席者は以下の12人です。
- ・今村聡・公益社団法人日本医師会副会長
- ・大道道大・一般社団法人日本病院会副会長
- ★落合孝文・一般社団法人日本医療ベンチャー協会理事
- ★金丸恭文・フューチャー株式会社代表取締役会長兼社長グループCEO
- ・黒木春郎・医療法人社団嗣業の会理事長
- ・島田潔・板橋区役所前診療所院長
- ・高倉弘喜・国立情報学研究所アーキテクチャ科学研究系教授
- ・高林克日己・医療法人社団鼎会理事、三和病院顧問、千葉大学名誉教授、一般社団法人日本内科学会
- ・南学正臣・東京大学大学院医学系研究科腎臓・内分泌内科学教授、公益社団法人日本医学会
- ・袴田健一・弘前大学消化器外科学教授、一般社団法人日本外科学会代議員
- ・山口育子・認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長
- ・山本隆一・一般財団法人医療情報システム開発センター理事長
出席者の顔ぶれから、この検討会の性質がわかります。
医師の代表や病院経営者、医学研究者だけでなく、医療ビジネスに関わっている人たち(★印)も参加していることから、今回の見直しは、効率化や費用対効果やコストやビジネス化についても検討されます。
このことは、7つの見直しポイントにもくっきり表れています。
見直しポイント7項目は患者の利便性を高めるか
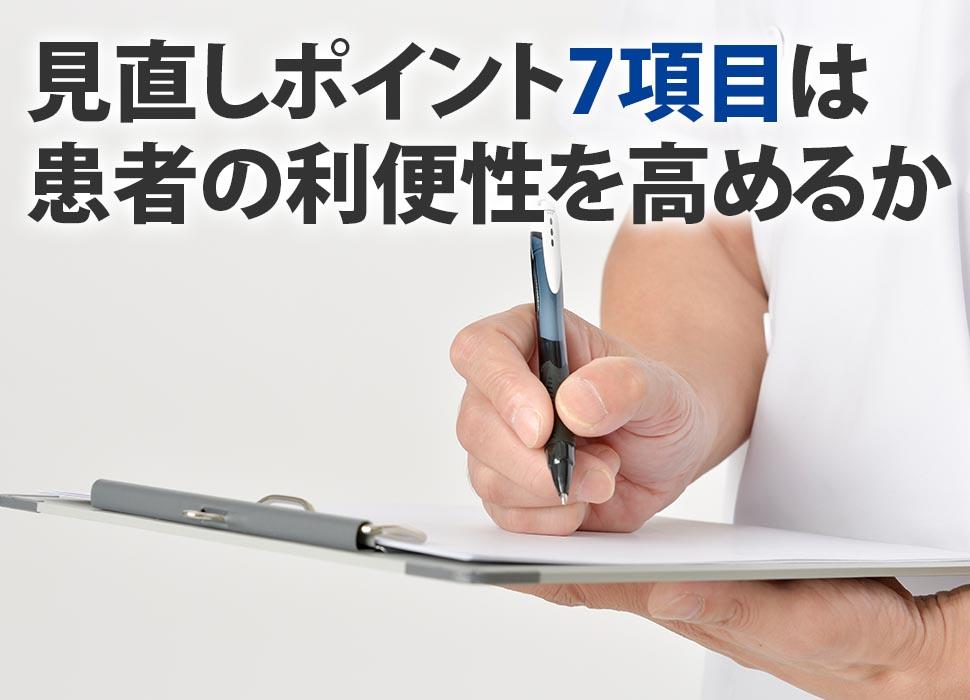
オンライン診療の見直し検討会は、次の7項目に焦点を当てて、オンライン診療制度を改善していきます。
- ①オンライン受診勧奨と遠隔健康医療相談等の整理
- ②対面診療との組み合わせ及び初診対面診療の原則の例外の検討
- ③オンライン診療時の予測された症状等への対応
- ④同一医師による診療原則の例外の検討等
- ⑤セキュリティの観点に基づく適切な通信環境の明確化
- ⑥D to P with N(看護師等が診療を補助するオンライン診療)の明示
- ①オンライン受診勧奨と遠隔健康医療相談等の整理
- ⑦オンライン診療を実施する医師の研修必修化
このうち、患者に影響しそうな項目について詳しくみていきます。
オンライン受診勧奨と遠隔健康医療相談等の整理
オンライン受診勧奨とは、医師が患者にオンラインを使って(インターネットを使って)受診をすすめることです。
遠隔健康医療相談とは、医師がオンラインで患者の健康医療相談を受けることです。
この2つがなぜ「問題」になっているのかというと、「正式なオンライン診療」との区別が不明瞭だからです。
正式なオンライン診療は、公的医療保険の対象になっているので、厚生労働省の規制が働きます。
しかし、オンライン受診勧奨や遠隔健康医療相談は、事実上任意であるため、厚生労働省の規制が働きません。
ところが、オンライン診療もオンライン受診勧奨も遠隔健康医療相談も、同じIT・インターネットシステムを使うので、
「やろうと思えば」オンライン受診勧奨や遠隔健康医療相談という形式で、ほとんどオンライン診療と同じことができてしまうわけです。
これではオンライン診療制度が「骨抜き」になってしまいます。
そこで厚生労働省には、つぎのようなルールがあります。
- ・オンライン受診勧奨では、具体的な病名を挙げてその病気にかかっていることを患者に伝えたり、一般用医薬品の使用を指示したり、処方を行ったりすることはできない。
- ・遠隔健康医療相談では、患者などの相談者の個別的な状態を踏まえた医学的判断を行うことはできない。
しかし、このルールはオンライン(インターネット)を使った医療の可能性を狭めています。
そこで、検討会では、次のようにルールを緩和することができないか、考えていくことにしました。
- ・オンライン受診勧奨で、①発症する可能性がある具体的な病名を挙げて、医学的な判断を行って受診をすすめる、②一般用医薬品を用いた自宅療養をすすめる、③医学的判断に基づく治療方針を伝える――といったことをできるようにする
- ・遠隔健康医療相談で、患者個人の心身の状態に応じた医学的な助言を行うことを可能にする
もし実際にこうしたことができるようになると、オンライン受診勧奨や遠隔健康医療相談で「かなりのことができる」ようになるでしょう。
つまり、インターネットを使った医療の可能性が広がるわけで、患者の利便性は向上しそうです。
参考:オンライン受診勧奨と遠隔健康医療相談等の整理
https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000473052.pdf
対面診療との組み合わせ及び初診対面診療の原則の例外の検討
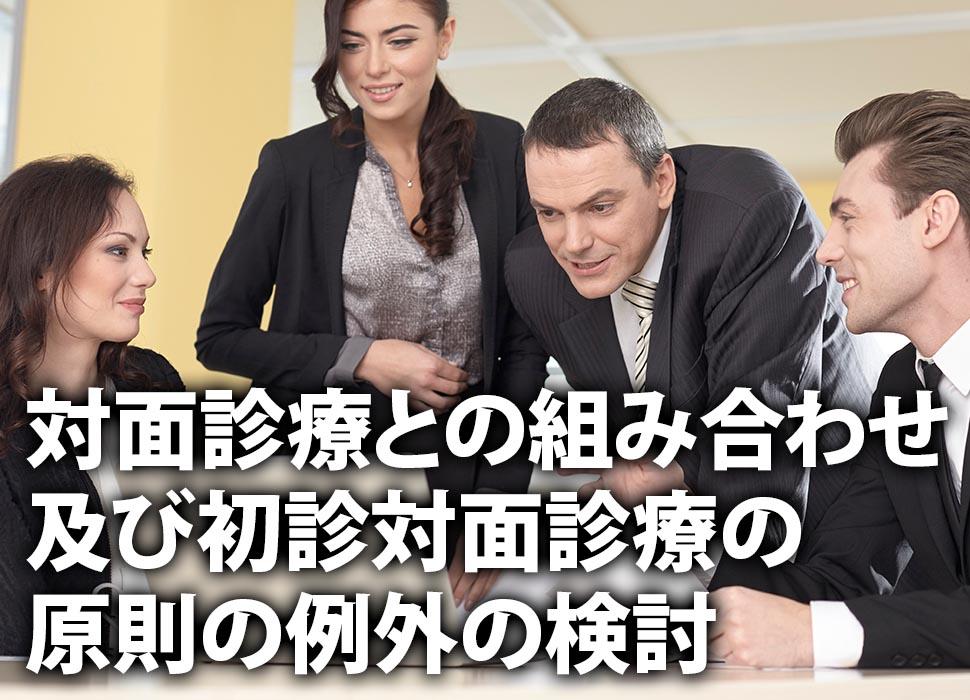
現行のオンライン診療が「使いにくい」と指摘されるのは、①初診から半年間は対面診療を行わなければならない、②オンライン診療がスタートしても3カ月に1回は対面診療を行わなければならない――からです。
これでは、発症から半年以内に治ってしまう病気の患者はオンライン診療を使うことができません。
また、オンライン診療が始まっても、患者は対面診療を受けるために3カ月に1回はクリニックに行かなければならず、オンライン診療を受けるメリットが減ってしまいます。
そこで今回の検討会では、対面診療とオンライン診療の組み合わせの例外や、初診対面診療の原則の例外を考えていくことになりました。
これも患者の利便性の向上が期待できます。
https://www.m3.com/open/iryoIshin/article/584683/
同一医師による診療原則の例外の検討等
現行のオンライン診療を「使いにくく」している規制は、まだほかにあります。
対面診療を行った医師がオンライン診療を行わなければならない、というルールです。
つまり、患者は対面診療をしてくれた医師のオンライン診療しか受けられない、ということです。
このルールは、複数人の医師がいるクリニックや病院で、対面診療とオンライン診療を分業することを阻んでいます。
例えば、インターネットやIT機器が苦手でオンライン診療を行っていない医師の対面診療を受診してしまった患者は、オンライン診療を受けられないわけです。
そうなると患者が困るだけでなく、オンライン診療を行っていない医師を敬遠する患者が出てくる可能性もあるので、医師側にも不利です。
そこで今回の検討会では、この「同一医師による診療」の例外づくりを検討します。
チーム医療や複数主治医制を活用し、対面診療をしていない医師がオンライン診療を実施する道を探るわけです。
対面診療が得意な医師は対面診療に集中し、オンライン診療が得意な医師がオンライン診療に集中すれば治療効果が高まることがで期待できますし、医師の負担も軽減できそうです。
D to P with N(看護師等が診療を補助するオンライン診療)の明示
DはDoctor(医師)、PはPatient(患者)、NはNurse(看護師)を意味します。
D to Pは「医師と患者の間の医療」を意味します。with Pは、医師と患者の間の医療に看護師が積極的に関与することを意味します。
オンライン診療は在宅医療でも使われています。
在宅医療では訪問看護師が活躍しています。したがって在宅医療でのオンライン診療では、D to P with N「医師と看護師が密接に連携した医療」が特に重要になってきます。
そこで今回の検討会では、看護師がオンライン診療で行うことができる業務を明記することを目指します。
オンライン診療を実施する医師の研修必修化

検討会では、オンライン診療を実施する医師に、研修の受講を必修にするかどうかも検討します。
オンライン診療は新しい医療なので、患者としても、オンライン診療研修を受けた医師のほうが安心できます。
検討のスタートラインは現場の医師の要望から?
オンライン診療が本格的にスタートしたのは2018年4月です。
今回の見直し検討会の初会合は2019年1月です。
つまり厚生労働省は、新しい制度をはじめてわずか9カ月で見直しが必要であると判断したわけです。
常に慎重を期して新制度を導入する厚生労働省としては「異例」といえるでしょう。
厚生労働省を動かしたきっかけのひとつが、今回の検討会のメンバーである黒木春郎氏が会長を務める日本オンライン診療研究会(※1)です。
日本オンライン診療研究会は、オンライン診療をどのような患者に提供すべきかを研究するグループで、20の診療科の120人の医師などで構成されます。
厚生労働省は、オンライン診療の見直し検討会の資料に、日本オンライン診療研究会の意見・要望を採用しています。
黒木氏たちの意見・要望は次のとおりです(※2)。
- ・オンライン診療を、外来、入院、訪問診療と並ぶ診療形態のひとつとして発展させてほしい
- ・同一医師診療の原則を見直してほしい
- ・オンライン診療で処方ができるようにしてほしい
- ・緊急避妊薬について初診からオンライン診療を行っている医師がいるが、原則から外れていいのか、明確にしてほしい
- ・セカンドオピニオンの位置づけを明確にしてほしい
いずれも患者の利便性が向上しそうなものばかりですし、今回の見直し7項目にも影響を与えています。
厚生労働省がいち民間団体の意見・要望を受け入れ、それを制度の見直しのベースにすることも「異例」です。
日本オンライン診療研究会の活動が高く評価された証(あかし)といえるでしょう。
※1:https://online-m.org/about/
※2:https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000473053.pdf
まとめ~どのように変わるのか楽しみ

厚生労働省がオンライン診療の見直しに素早く着手したのは、オンライン診療がインターネットシステムやITシステムに依存しているからでしょう。
インターネットもITも、日進月歩で進化しています。
したがって、インターネットとITを使うオンライン診療も、さらに進化できるポテンシャルを秘めているわけです。
見直し検討会が生み出す「新オンライン診療」はどのような形になるのでしょうか。
結果がとても楽しみです。
料金設定も「予約料500円+お薬の送料一律500円+お薬代」のみとなっております。
厚生労働省の告知に基づき、当クリニックでの初診は来院で受診して頂いた上で、
再診時よりオンライン診療による受診が可能となります。
この記事を読んだ方は他にこんな記事も読んでいます
-
オンライン診療(遠隔診療)の高血圧の治療はどう行われるのか
2018年4月17日
高血圧の治療はオンライン診療(遠隔診療)との相性が良さそうです。東京女子医科大学が、オンライン診療(遠隔診療)による高血圧治療の効果を確かめる実証研究を行っているほか、いくつかのクリニックが「...
詳しく見る >
-
北海道の離島にオンライン診療が届く日【遠隔診療が地方医療を救う】
2018年5月2日
もし北海道旅行を計画して、絶品のウニとアワビを食べたいと思ったら、奥尻島は必ず候補地の1つに加えておいてください。北海道の南西部の日本海に浮かぶこの島は、寒流と暖流に囲まれたおかげで良質な漁場...
詳しく見る >
-
ネットで日本中の健康情報を集めろ! 東大と厚労省が世界初のプロジェクト
2018年8月9日
オンライン診療(遠隔診療)は、遠くにいる患者と医師を結ぶ画期的な医療です。 こんなに素晴らしい医療をつくることができたのは、インターネットのおかげです。 そのインター...
詳しく見る >
-
ITはコミュニケーションを高めるから医療の質を高める
2018年10月12日
「日本の医療はもっとIT化したほうがよい」と言ったら、驚く人がいるのではないでしょうか。 「日本の医療は世界最高水準だから、十分IT化されているはずだ」と思った方は、考えをあらためたほうがよ...
詳しく見る >
-
あのLINEがオンライン医療に進出
2019年5月10日
無料チャットアプリのLINEを運営するLINE株式会社が、オンライン医療に進出しました。 LINEは人々のコミュニケーションを劇的に変えましたが、今度は医療にどのような変革をもたらそうとしている...
詳しく見る >
-
精神科領域でオンライン診療の医師向け「手引書」が完成
2019年2月14日
オンライン診療(遠隔診療)を行っているクリニックの医師にとって、待ち望んでいたものがようやく完成しました。 国内初の、オンライン診療を行っている医師向け「手引書」が、慶応義塾大学医学部などに...
詳しく見る >