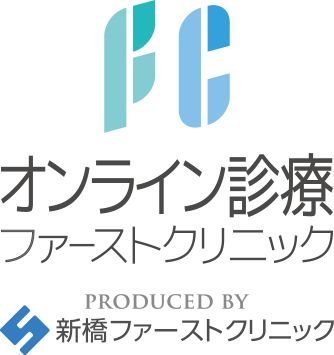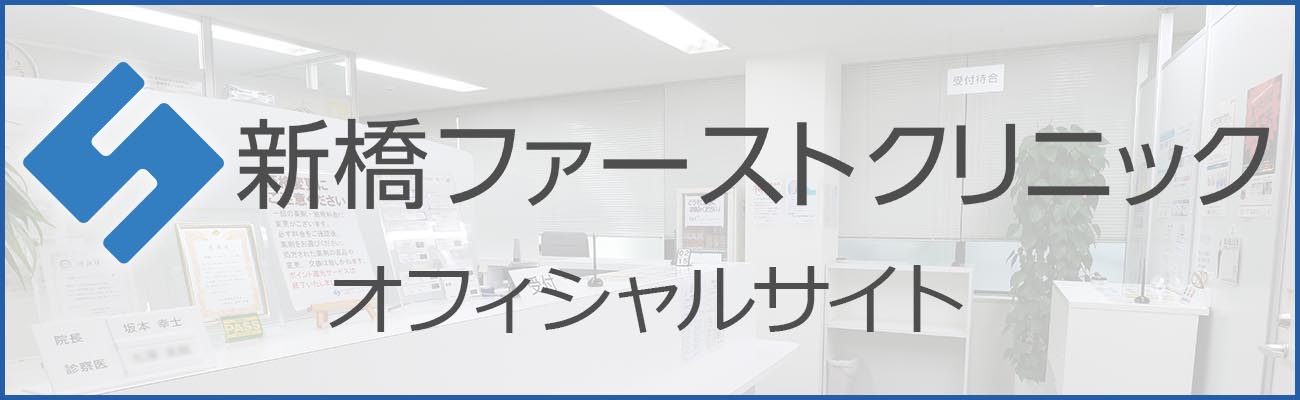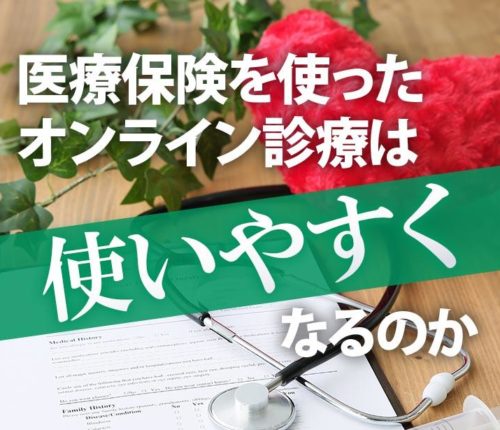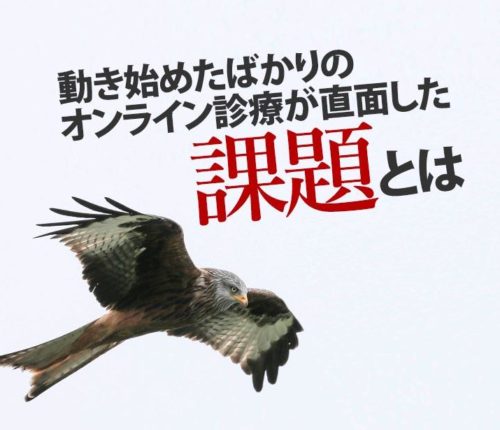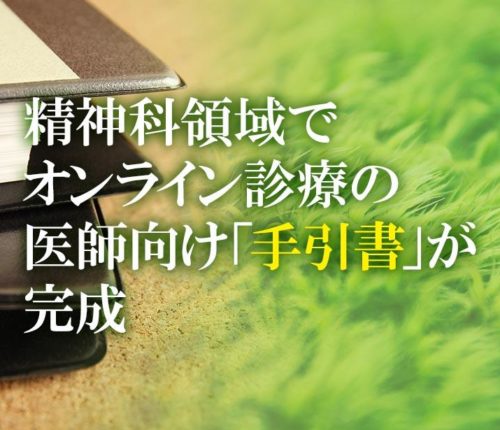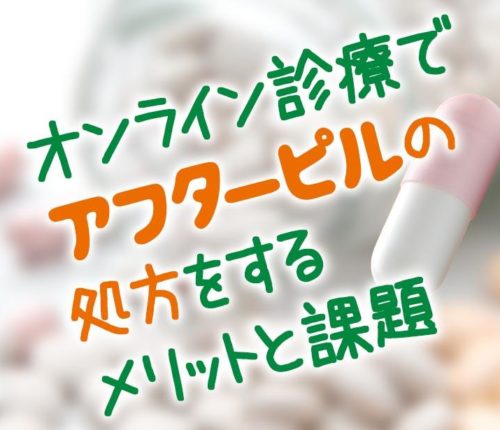- 2025/12/03:クリニクスによるオンライン診療は終了いたしました
- 2025/02/12:LINEでオンライン診療を受けられるようになりました(詳しくはこちら)

Telemedicine Report
記事リリース日:2018年7月2日 / 最終更新日:2019年1月21日
オンライン診療(遠隔診療)の未来を左右する?
福岡市の事業が注目されるワケ
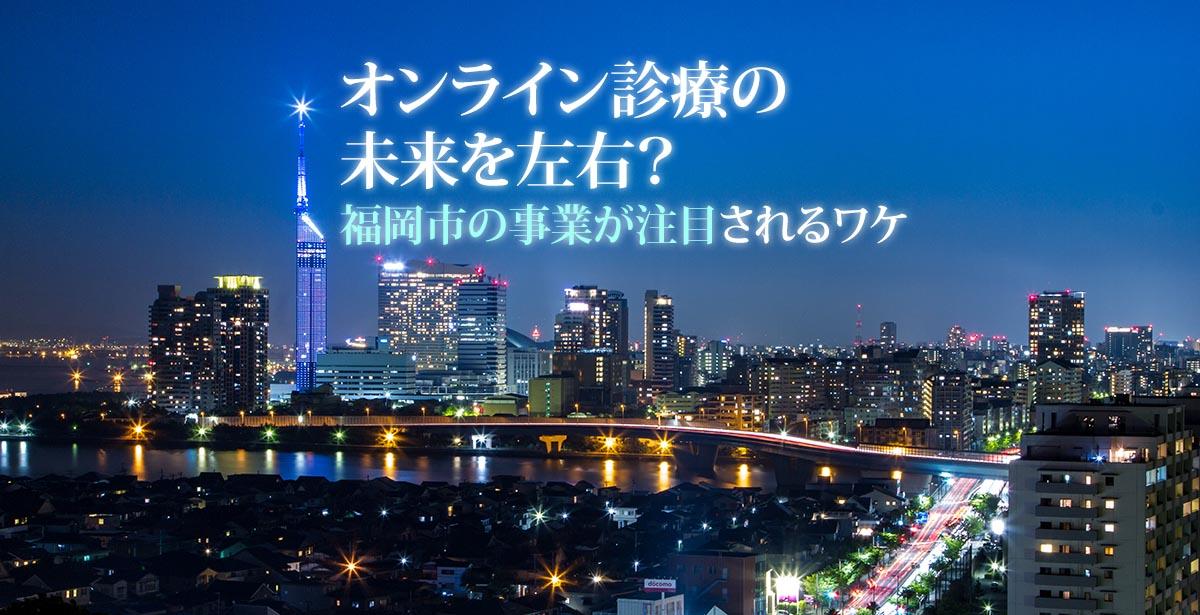
厚生労働省は当初、オンライン診療(遠隔診療)を離島やへき地など、患者と医師が繋がりにくい場所での利用を考えていました。医師の訪問が難しい場所に医療を届ける、という考え方は合理的といえます。
ところが、オンライン診療(遠隔診療)を使えば使うほど様々な可能性が判明し、実は人口が多い場所で使っても効果的であるということが分かってきました。

福岡市の人口は約160万人で、日本で5番目に人口が多い市です。福岡市で行われているオンライン診療(遠隔診療)の取り組みは、現代の医療の課題を解決するカギになりそうです。
目次
「在宅患者が2.5倍になる」という危機感
福岡市は「福岡市健康先進都市戦略」を定めていて、オンライン診療(遠隔診療)の取り組みは7つのメニューのうちの1つです。
福岡市は離島でもへき地でもありませんが、それでもオンライン診療(遠隔診療)に取り組む方針を固めたのは、ある危機感があったからです。
それは、
在宅医療を必要とする患者が2013年の8,724人から、2025年には2.5倍の21,679人になる、という推定です。
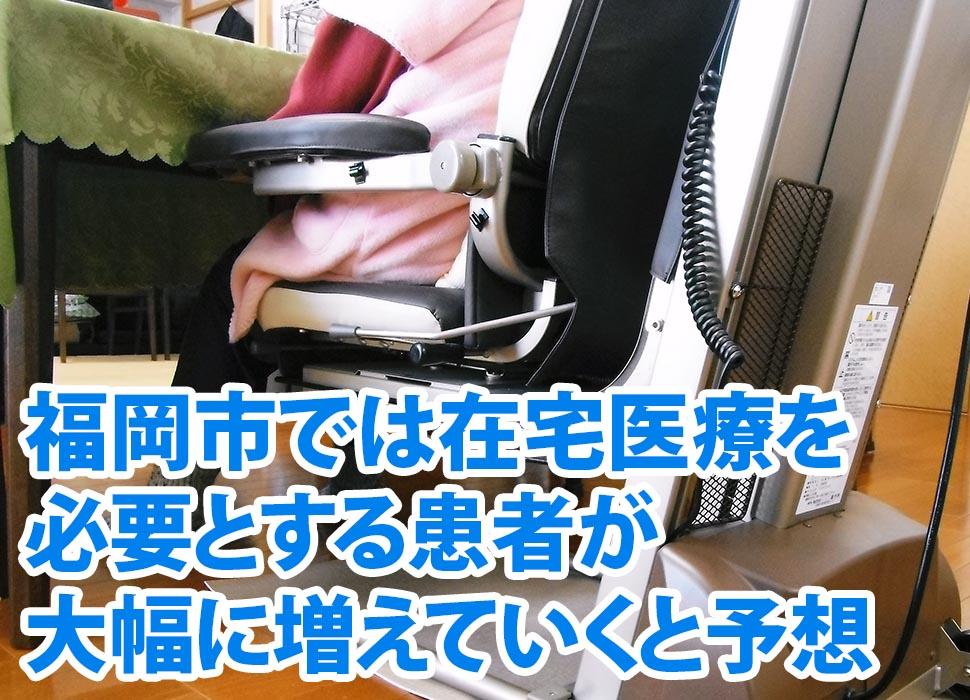
在宅医療とは、かかりつけ医が患者宅を訪問する医療サービスです。
在宅患者が2.5倍になることは確実ですが、在宅医療に携わるかかりつけ医を2.5倍に増やすことは現実的ではありません。
これは福岡市内の医療界が抱える大きな課題といえます。
かかりつけ医を遠隔診療で鍛える?
そこで福岡市は、オンライン診療(遠隔診療)を使って在宅医療の効率化を図ろうと考えました。
つまり、かかりつけ医にオンライン診療(遠隔診療)を導入してもらい、1人のかかりつけ医が診る在宅患者を増やそうという戦略です。
かかりつけ医をオンライン診療(遠隔診療)で鍛え上げようというのです。
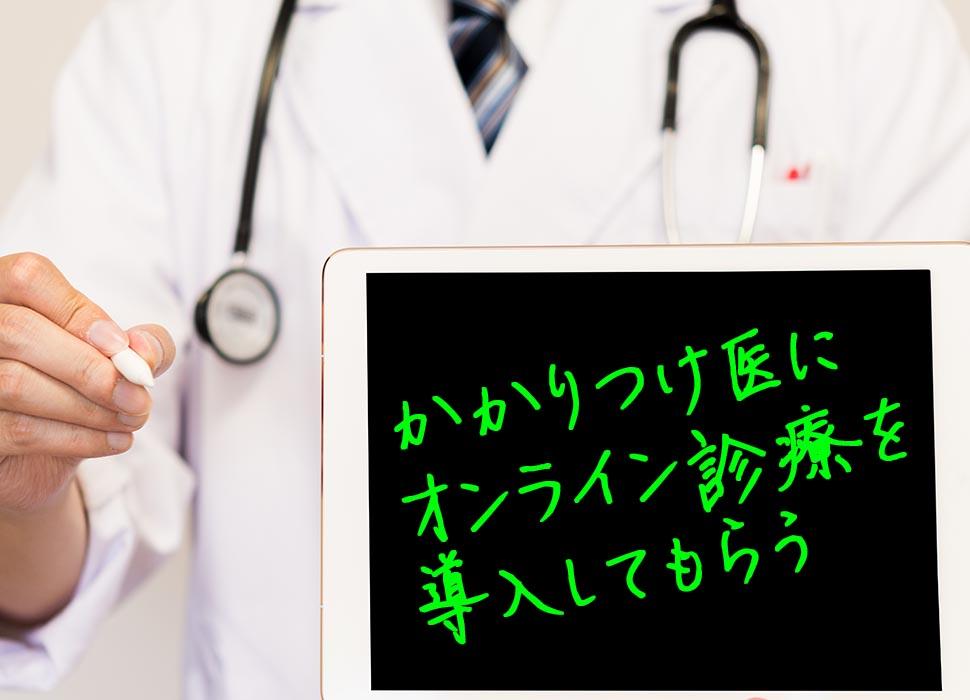
問診、診察、モニタリングの機能を強化する
福岡市の大々的なオンライン診療(遠隔診療)の実証事業を手掛けるのは、福岡市、福岡市医師会、医療法人社団鉄祐会(以下鉄祐会、東京都)、株式会社インテグリティ・ヘルスケア(以下IH社、東京都)の4者です。
そして九州厚生局もオブザーバーとして参加しています。九州厚生局は厚生労働省の出先機関ですので、国も福岡市の取り組みに注目しているというわけです。
鉄祐会は東京で訪問診療のクリニックを複数展開しています。IH社は遠隔診療「YaDoc(ヤードック)」を運営している会社です。
鉄祐会の理事長とIH社の会長は、東大卒の医師で宮内庁侍医や大手金融会社の社員などの経歴を持つ武藤真祐氏です。
福岡市健康先進都市戦略における遠隔診療の実証事業の正式名称は「ICTを活用した『かかりつけ医』機能強化事業」といいます。
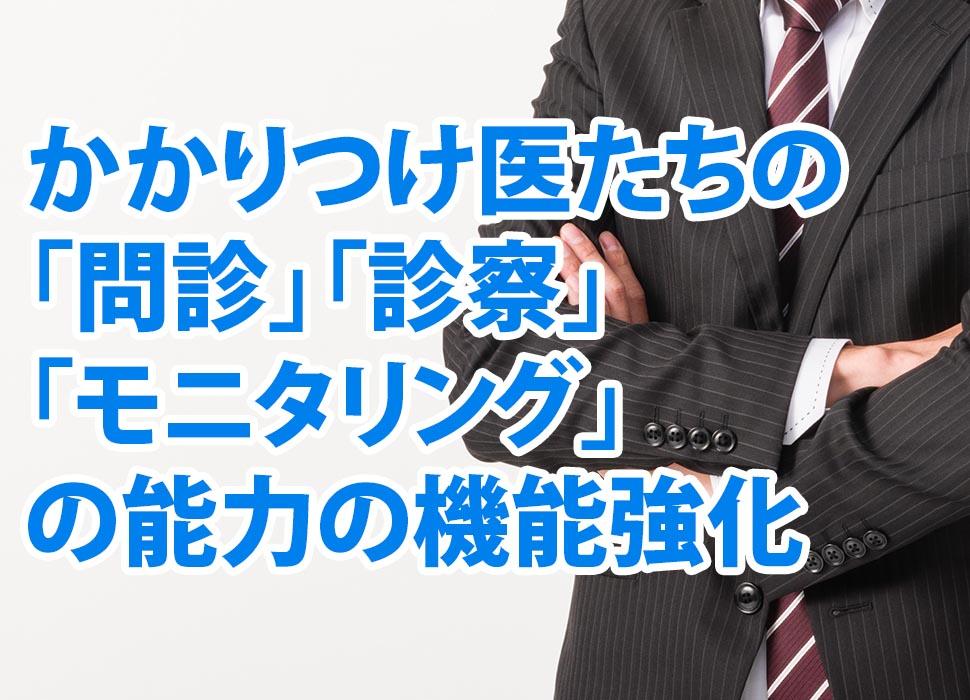
この事業で機能強化を狙うのは、かかりつけ医たちの「問診」「診察」「モニタリング」の能力です。
医療の質と時短とコストが改善するか確かめる
問診とは、適切な検査や的確な診察を行うために、医師が患者に病歴や症状を尋ねることです。
診察とは、治療方針を決定するために、医師が患者を調べることです。
モニタリングとは、検査機器を使って患者の状態を監視、観察、測定、点検、記録することです。
ここでいくつか疑問が沸きます。
問診も診察もモニタリングも、福岡市ほどの大都市であれば、どの医療機関でも完璧にこなしていそうに思えます。いまさらオンライン診療を導入して、医師の問診力、診察力、モニタリング力が、これまで以上に向上するのでしょうか。
または、オンライン診療(遠隔診療)を導入することで、問診と診察とモニタリングの時間が短縮したり、必要な経費が安くなったりするのでしょうか。
福岡市の取り組みはまさに、オンライン診療(遠隔診療)によって医療の質と時短とコストが改善するのかどうかを確かめるために行うのです。
医師と患者の距離が数メートルでオンライン診療(遠隔診療)を使う斬新さ
福岡市のオンライン診療(遠隔診療)の実証事業には、20の医療機関が参加しています。2017年春に参加したMクリニックの院長はマスコミの取材に対し「すでに患者にも医師にもメリットが生まれている」と話しています。
Mクリニックのようなオンライン診療(遠隔診療)の活用法は、恐らく厚生労働省は予測していなかった事でしょう。
離島やへき地での利用を考えていた厚生労働省にとって、オンライン診療(遠隔診療)を使う医師と患者の間の距離は、数十キロから数百キロを想定していたはずです。
ところがこのMクリニックのオンライン診療(遠隔診療)は、医師と患者が数メートルしか離れていないのです。
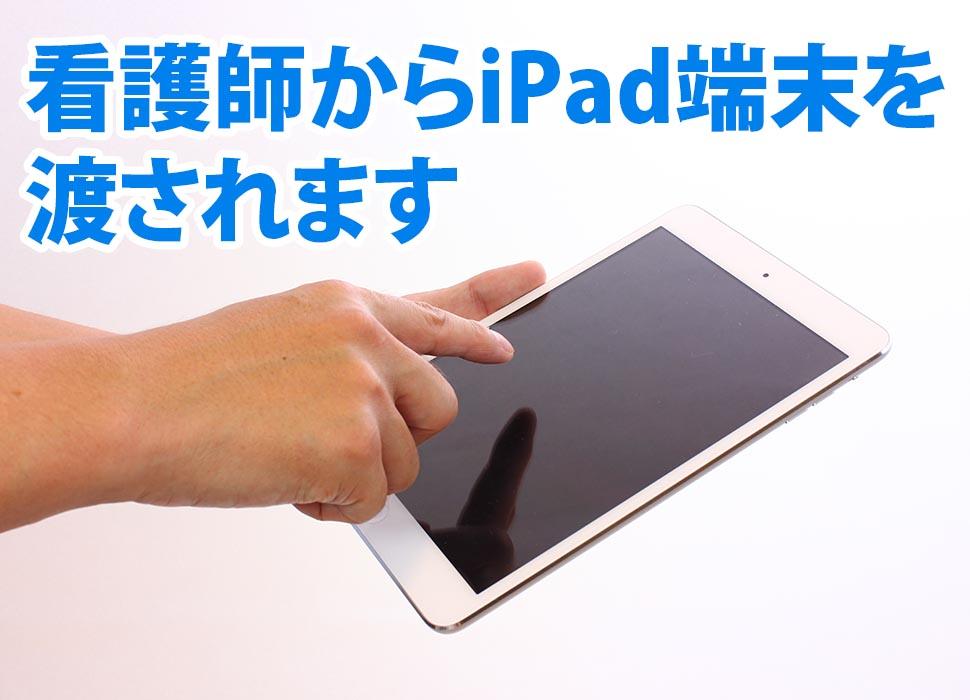
Mクリニックの患者は自宅でオンライン診療(遠隔診療)を受けるのではなく、クリニックに足を運びます。
患者がクリニック内の待合室に座ると、看護師からタブレットのiPadを渡されます。患者はiPadに出てくる質問に次々答えていきます。
例えば、その患者が喘息をわずらっていれば「朝早く目覚めましたか?」や「息切れの頻度はどれくらいですか?」と言った質問が出てきます。
また患者が、喫煙者に多く発症する慢性閉塞性肺疾患(COPD)を発症していれば、iPadには「咳はいつも出ますか?」「痰が詰まっている感じがありますか?」「息苦しいですか?」といった質問が出ます。
患者は質問された症状を1~5段階評価してiPadに打ち込んでいきます。
これは初診時の問診の風景ではありません。Mクリニックに来る患者は、毎回この質問に答えるのです。
iPadは直感的に操作できますし、質問の内容は簡単です、そして待ち時間を活用しているので患者の負担はほとんどありせん。
iPadに入力されたデータは、瞬時に診察室の医師のパソコンに送られ、さらに過去のiPad問診のデータも表示されるので、患者が診察室に入ってきた途端に医師が「薬の効果が出ているようですね」と声をかけることができるのです。
問診と診察の欠点を補う力は立証できた
通常、クリニックでの生活習慣病の診察は数分で終わりますが、この方式であれば「とても濃厚な3分診療」が行えます。
なにしろ患者が目の前に現れるころには、医師の頭に中には、今日の患者情報と前回の患者情報が入っているわけですから。
問診や診察では、以前からある欠点が指摘されていました。
それは、患者は一般的に、症状を正確に伝えることが苦手である、ということです。また医師は一般的に、患者の状態を正確に聞き取ることが苦手である、ということです。
もちろん患者にも医師にも個人差はありますが、伝えることの難しさと、聞き取ることの難しさは、問診と診察の質を低下させます。
問診と診察の質を向上させる「秘密」は、iPadが出す質問にあります。
iPadに出てくる質問は、例えば喘息患者には「喘息コントロールテスト(ACT)」に沿った内容になっています。
また慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者が答えるiPadの質問は、「COPDアセスメントテスト(CAT)」に沿った内容になっています。
ACTもCATも、国立大学などで使われている本格的なテストです。
つまり、より高度でより専門的な問診でも、iPadとオンライン診療(遠隔診療)を使えば簡単に行えるので、再診のたびに実施することができます。
問診が充実することで診察にも良い影響を及ぼす、というわけです。
地方都市の医師の進取の気性を引き出す
そしてこのMクリニックでのオンライン診療(遠隔診療)の導入事例では、もうひとつ興味深いことがあります。それは、Mクリニックの院長が、今回の福岡市の実証事業の前から、独自にインターネットを使った医療相談をしていた、ということです。
しかしMクリニックの院長は、この独自のインターネット医療相談を本格的には行っていませんでした。それは診療報酬が発生しないからです。
そこに福岡市医師会から、オンライン診療(遠隔診療)の実証事業への参加の呼びかけがあったので、Mクリニックの院長はすぐに応募したのです。
このエピソードは、地方の医師ほど最新技術の導入に意欲的であることを示しています。そして、現行の医療システムではそうした医師たちの意欲を十分に引き出せていないことも分かります。
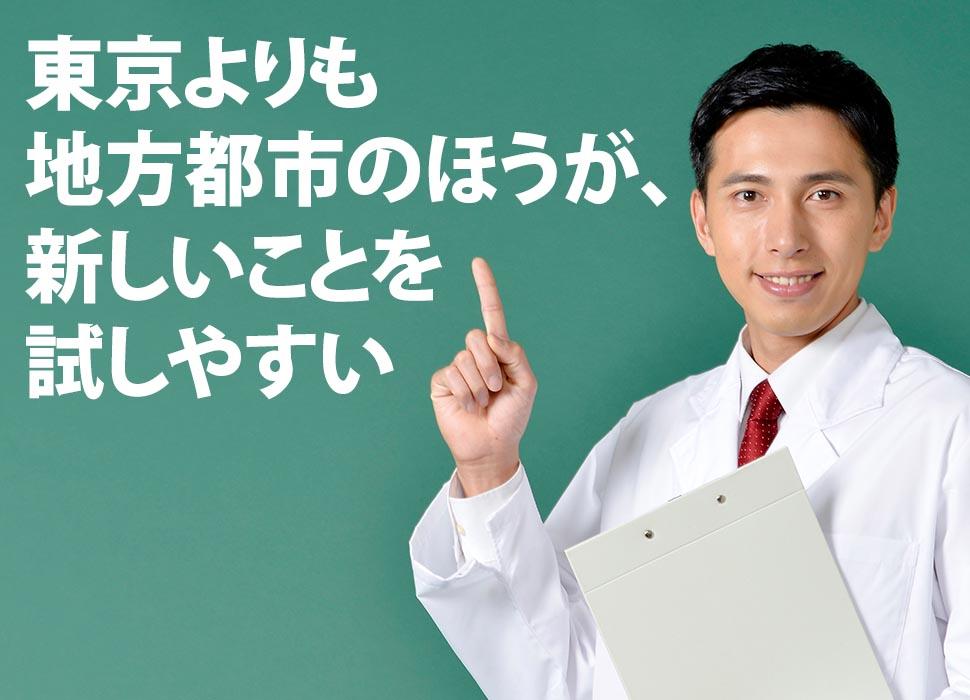
また東京よりも地方都市のほうが、色々なしがらみが小さいため新しいことを試しやすいのでしょう。
新しいオンライン診療(遠隔診療)の形を模索する取り組みが福岡市で行われているのは、偶然ではないようです。
まずは「手入力」から、次は検査機器をネット接続
以上見てきたように、訪問診療医やかかりつけ医の機能強化のうち、問診と診察については遠隔診療によって質と効率化の向上が果たせそうです。
それでは次に、モニタリング力をオンライン診療(遠隔診療)でどのようにして向上させるのかを見てみましょう。
モニタリングとは、検査機器を使って患者の状態を監視、観察、測定、点検、記録することです。
福岡市の実証事業では、オンライン診療(遠隔診療)がもたらすモニタリングへの効果は、老人ホームなどの介護施設で行っています。
現行は、介護施設の看護師や介護職員が、入居者の体温や血圧などのバイタルを計測し、その数値を手で入力して医師にデータを送っています。
将来的には、高齢者の体に身に付けた血圧計や血糖値センサーをインターネットにつなげ、検査機器が自動的にデータを送る方法に移行していきます。
オンライン診療(遠隔診療)を診療報酬の対象に、そのためにはエビデンスが欠かせない
福岡市のオンライン診療(遠隔診療)実証事業は、IH社が事業費の大部分を負担しています。企業としては先行投資ということになりますが、一社の努力では限界があります。
IH社も、そして実証事業に参加している医療機関も、目指すところはオンライン診療(遠隔診療)が公的医療保険の対象になることです。
しっかりとしたオンライン診療(遠隔診療)を行って相応の売上を確保し、経営が安定することを目標にしているのです。
そのためには、この実証事業で「オンライン診療(遠隔診療)は良いシステムである」というエビデンスを集めなければなりません。エビデンスとは根拠という意味です。
エビデンスは数値で示さなければなりません。
つまりオンライン診療(遠隔診療)の導入により、医療の質がどれだけ上がったのか、コストダウンがどれほど図ることができたのか、といった結果を数値化で明確にする必要があります。
まとめ:中央省庁の強力なアピールとなるか
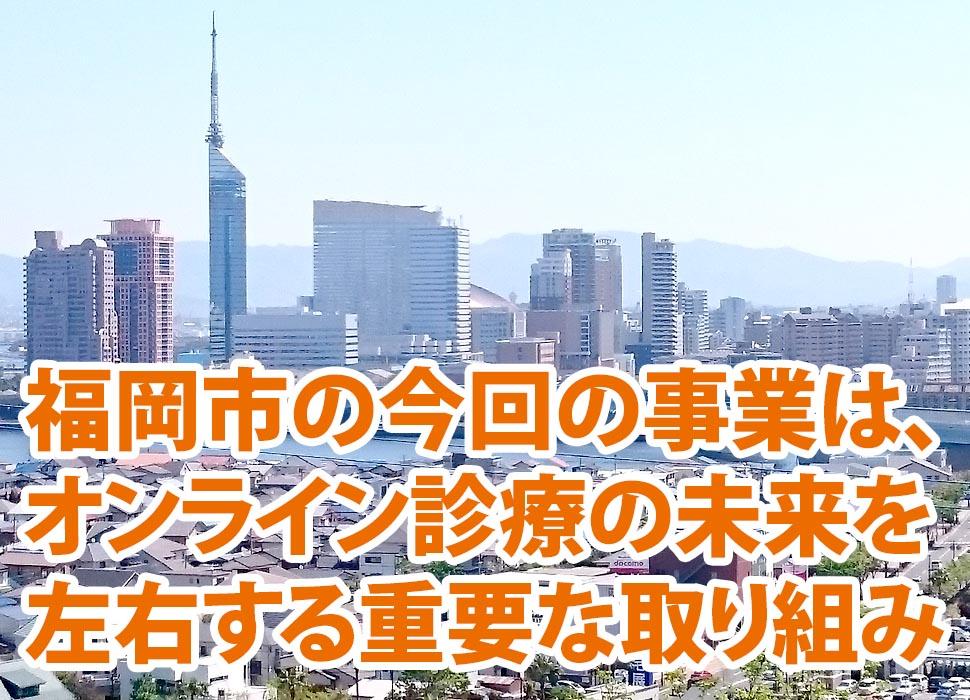
この実証事業には、九州厚生局という厚生労働省の出先機関がオブザーバーとして参加していると紹介しました。つまり福岡市の遠隔診療の取り組みを、厚生労働省の官僚がしっかり見届けているということです。
実証事業が成功すれば、中央省庁へのアピールはかなり強力なものになるはずです。
そういった意味では、福岡市の今回の事業は、オンライン診療(遠隔診療)の未来を左右する重要な取り組みといえるのです。
料金設定も「予約料500円+お薬の送料一律500円+お薬代」のみとなっております。
厚生労働省の告知に基づき、当クリニックでの初診は来院で受診して頂いた上で、
再診時よりオンライン診療による受診が可能となります。
この記事を読んだ方は他にこんな記事も読んでいます
-
医療保険を使ったオンライン診療は“使いやすく”なるのか
2019年1月17日
2018年4月1日は、日本のオンライン診療(遠隔診療)の歴史上、よい記念日でもありますが、よくない記念日としても記録されるでしょう。 よい記念日になるのは、このときからオンライン診療が本...
詳しく見る >
-
動き始めたばかりのオンライン診療が直面した課題とは
2018年9月5日
医療保険制度上のオンライン診療(遠隔診療)が本格スタートから約3カ月が経過した2018年6月下旬、「オンライン診療カンファレンス」というイベントが開かれました。 このな...
詳しく見る >
-
人工知能はどうやって人を治すのか【テクノロジーが医療を変える】
2018年7月12日
自分が病気をして病院に行ったとします。受付で「医師による診察を希望しますか。それとも人工知能(AI)による診察を希望しますか」と聞かれたらどちらを選択するでしょうか。 恐らく多くの人は、「A...
詳しく見る >
-
精神科領域でオンライン診療の医師向け「手引書」が完成
2019年2月14日
オンライン診療(遠隔診療)を行っているクリニックの医師にとって、待ち望んでいたものがようやく完成しました。 国内初の、オンライン診療を行っている医師向け「手引書」が、慶応義塾大学医学部などに...
詳しく見る >
-
オンライン診療(遠隔診療)でアフターピルの処方をするメリットと課題
2018年11月9日
アフターピルは緊急避妊薬といい、性交後に妊娠を望まない女性が飲む薬です。この薬によって高い確率で避妊ができます。 通常のピルは月経の周期に合わせて飲むのが一般的ですが、こちらは性交後に飲...
詳しく見る >
-
【オンライン診療(遠隔診療)の経済学】②どんな企業が参加しているの?
2018年5月25日
※本記事はシリーズとなっておりますので前記事からの閲覧をおすすめ致します。前記事『【オンライン診療(遠隔診療)の経済学】①首相にプレゼンした「メドレー」ってどんな会社?』はこちらからご覧...
詳しく見る >