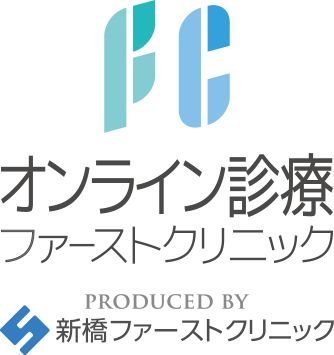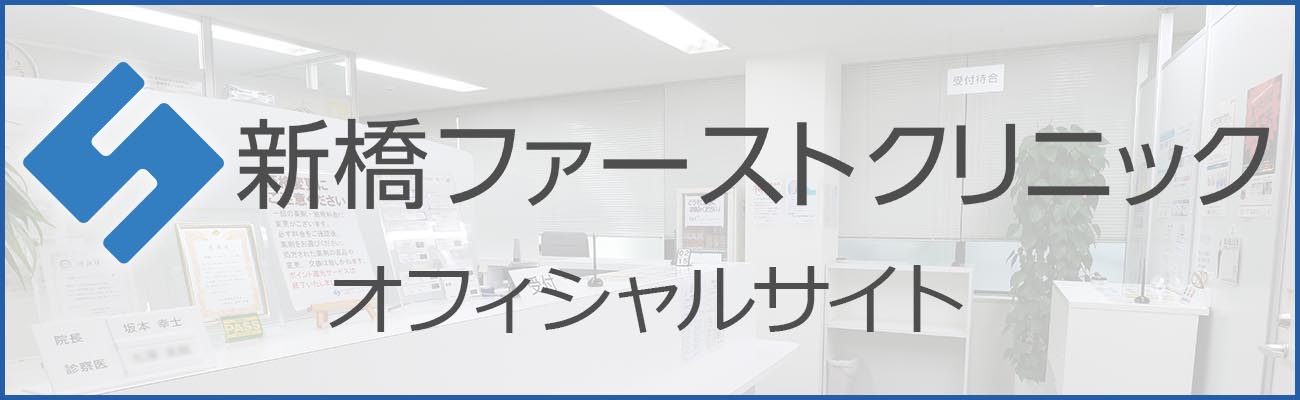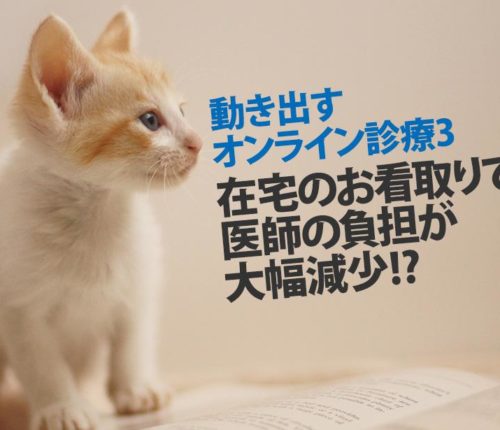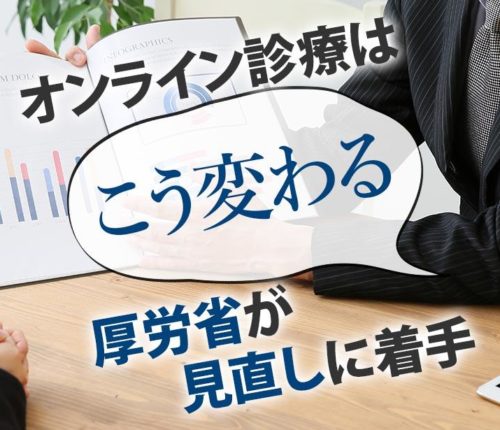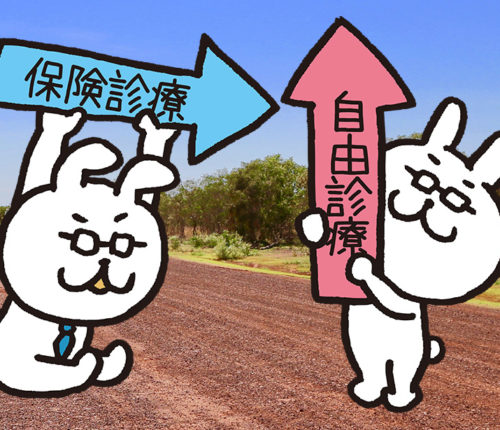Telemedicine Report
記事リリース日:2018年11月28日 / 最終更新日:2019年1月21日
オンライン診療(遠隔診療)の
利用が減っているのはなぜか
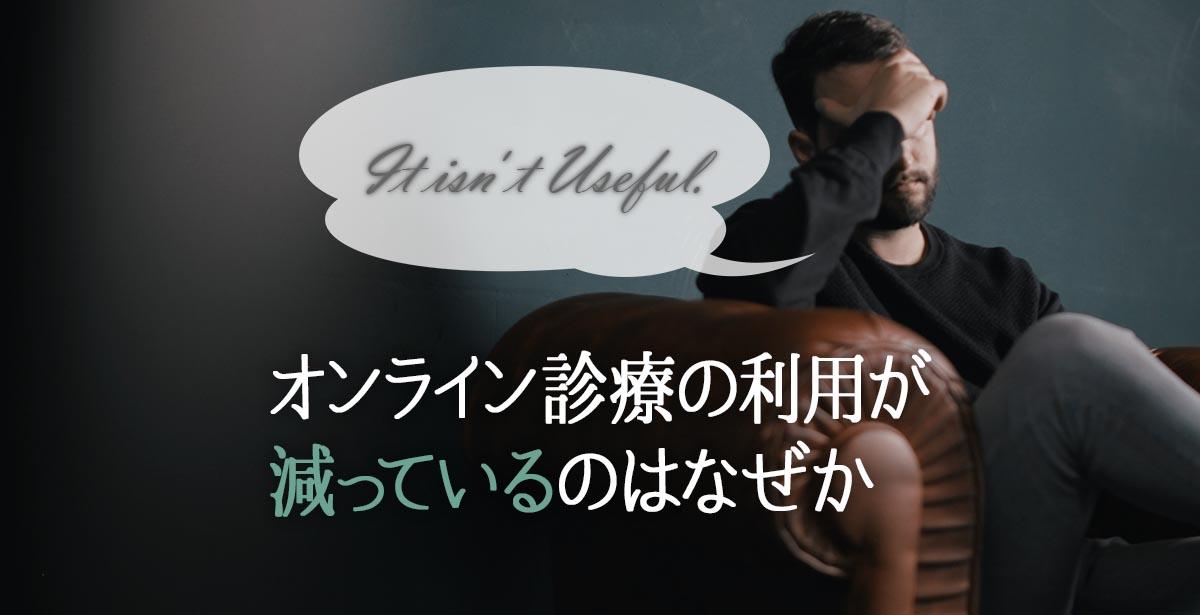
オンライン診療(遠隔診療)は2018年4月に、「公的医療保険の対象」になりました。
それまでは、スマホとネットを使ったオンライン診療は、電話による再診と同じ位置付けでしたが、それが「オンライン診療」という一つの診療方法として独立できたのです。
患者はわざわざクリニックに足を運ばなくても、手元のスマホのテレビ電話(ビデオ通話)だけで医師の診療が受けられるようになったのです。 医師や医療機関も、オンライン診療が“厚生労働省のお墨付き”が得られたことで、導入しやすくなりました。
したがってオンライン診療を利用する患者も導入するクリニックも増えるかと思われていましたが、実際はそうはなっていません。
ルールが厳しすぎることに原因があるようです。
目次
患者も医師も「便利で効果があるが使いにくい」

利便性が高く、なおかつしっかり制度化されたのに、なぜオンライン診療の利用が拡大しないのでしょうか。医療現場の様子をみてみましょう。
システム料を徴収するようになって患者が減った
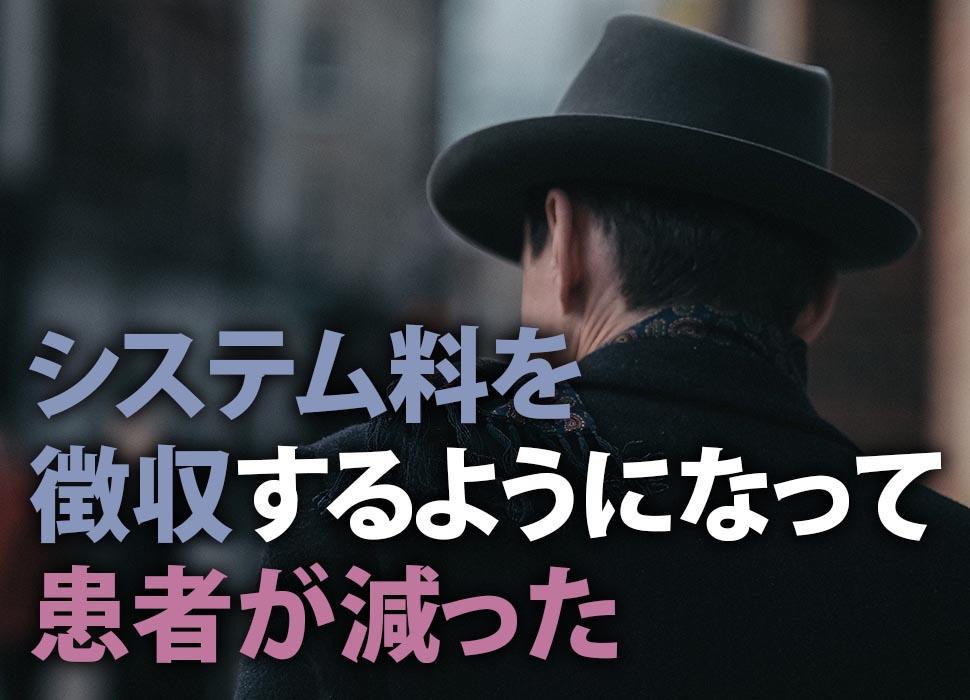
オンライン診療(遠隔診療)を利用する患者が減っていることを報じたのは、日本経済新聞社系のサイト、日経スタイルの記事です。
記事によると、埼玉県のある皮膚科クリニックは2016年11月からオンライン診療を導入しました。
これはかなり早い段階での取り組みといえ、クリニックの院長がオンライン診療の将来性に期待したことがうかがえます。
このクリニックでオンライン診療を利用する患者は順調に増え、オンライン診療が公的医療保険の対象になる前月の2018年3月には30人になっていました。
オンライン診療利用患者がこれだけ増えたのは、オンライン診療の持つシステムが合理的なものだったからです。
例えばアトピー性皮膚炎の治療の場合、症状が安定すれば同じ薬や同じ保湿剤を定期的に処方していくことになります。
オンライン診療を使えば、患者は同じ薬と保湿剤を手に入れるためだけにクリニックに行かなくて済みます。
医師としても、オンライン診療なら患部を画像で確認できるので、しっかり患者を診たうえで、“いつもと同じ処方”を行うことができます。
オンライン診療は、患者と医師の双方にとってメリットしかありません。
しかしこの皮膚科クリニックのオンライン診療の利用患者は、2018年8月には5人にまで減りました。
30人が5人になったので8割以上減ったことになります。
一体何故なのでしょうか?
利用患者が減った原因は、皮膚科クリニック側がオンライン診療患者からシステム利用料500円を徴収するようになったからです。
患者たちは「余計なお金がかかるなら、通院する」と判断したわけです。
ではなぜ皮膚科クリニックがシステム利用料を徴収するようになったのでしょうか。
それは、アトピー治療を含め皮膚科の病気は、公的医療保険を使ったオンライン診療の対象から外れた為です。
公的医療保険が使えないので、オンライン診療の実施に必要なコストをシステム利用料として患者に請求したわけです。
精神科と小児科でも相次ぎ取りやめ
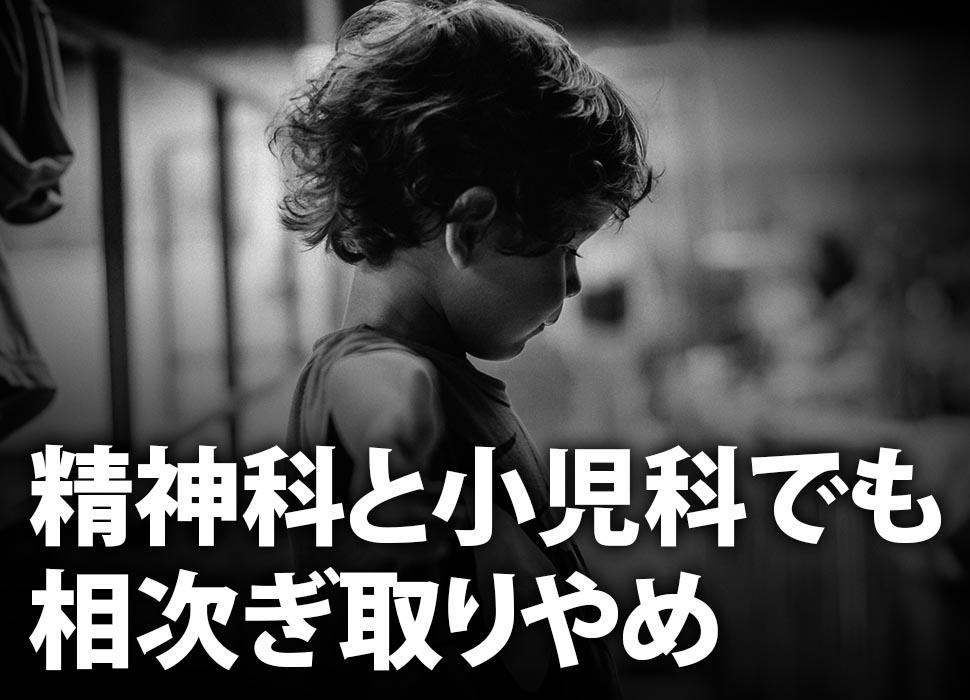
オンライン診療システム「クリニクス(CLINICS)」を開発・販売しているメドレーによると、オンライン診療は大きく減速している状況にあります。
同社がこれまでにクリニクスを販売した医療機関のうち、2018年9月までに数割程度の医療機関がクリニクスの使用を中断しました。
想定していたほどオンライン診療が拡大しない理由のひとつが、精神科と小児科で利用の中断が目立ったことです。
オンライン診療が公的医療保険の対象になる前は、精神科と小児科でオンライン診療の導入が目立っていました。
精神科や小児科の患者や家族は、通院困難に陥りやすい傾向が比較的高いため、通院しなくてよいオンライン診療が支持されたのです。
しかし、皮膚科疾患同様に、精神科疾患も小児科疾患も、公的医療保険が使えるオンライン診療の対象疾患にならなかったのです。
多くの患者が使えるようにしてほしい

先述の皮膚科クリニックの院長は「オンライン診療は患者の治療離脱を減らすのに有効な手段である」と述べています。
さらに院長は「皮膚科の病気の治療も、オンライン診療の保険診療の対象にしてほしい」と訴えています。
また、オンライン診療を導入している精神科医は、認知症やうつ病の患者の場合、症状が落ち着ていれば対面診療でも同じ薬を処方するだけのことが多いと指摘します。
それなら通院不要のオンライン診療のほうが患者のストレスを軽減でき、利便性が高いわけです。
この精神科医も「オンライン診療を利用できる条件を緩和して、多くの患者が使えるようにしていただきたい」と要望しています。
制度上の問題を指摘する声も
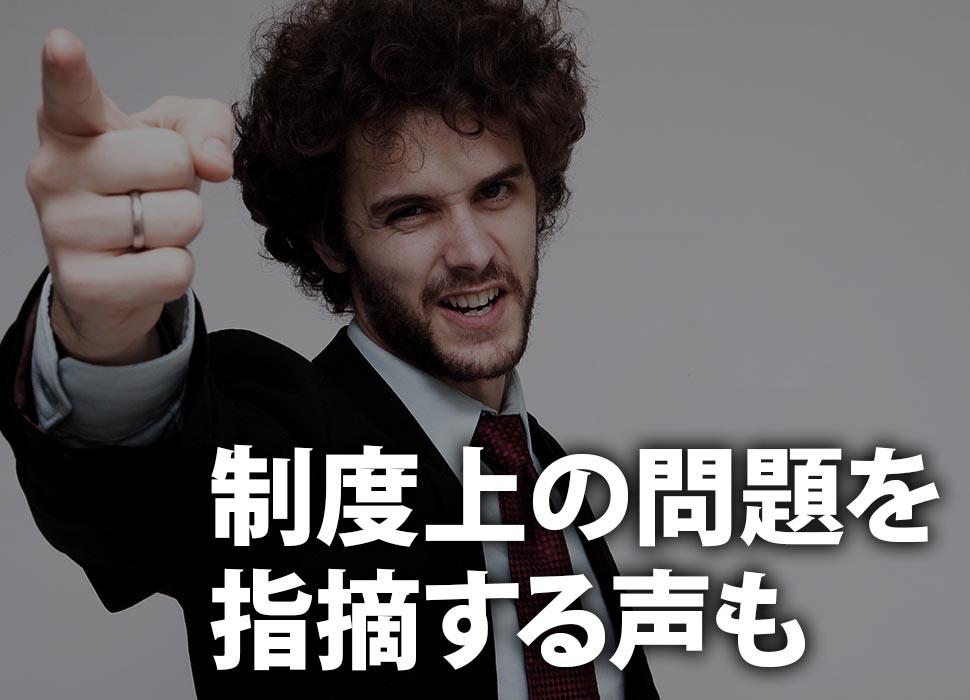
オンライン診療(遠隔診療)が便利で効果があるにも関わらず使いにくいのは、制度に問題があると指摘する声があります。
公的医療保険制度におけるオンライン診療の位置づけを確認しておきましょう。
現在のオンライン診療の仕組み
厚生労働省は、公的医療保険を使ってオンライン診療できる病気を、生活習慣病や難病など一部の病気に限定しました。
オンライン診療を実施してオンライン診療料(70点=700円)を請求できる病気は、以下の管理料や指導料を算定できる病気です。
- ・特定疾患療養管理料
- ・小児科療養指導料
- ・てんかん指導料
- ・難病外来指導管理料
- ・糖尿病透析予防指導管理料
- ・地域包括診療料
- ・認知症地域包括診療料
- ・生活習慣病管理料
- ・在宅時医学総合管理料
- ・精神科在宅患者支援管理料
これらの病気は具体的には次のとおりです。
結核、悪性新生物、甲状腺障害、糖尿病、高血圧性疾患、脳性麻痺、ダウン症等の染色体異常、脂質異常症、高血圧症、通院が困難で在宅療養が必要な精神疾患など
このなかに皮膚科疾患は含まれていませんし、小児科疾患や精神科疾患は含まれていますがいずれも治療が困難な病気ばかりです。
オンライン診療の対象となる病気のなかに、オンライン診療を導入しづらい病気も含まれていると指摘する声もあります。
つまりここには、いつもと同じ処方せんを渡すだけであれば、対面診療からオンライン診療に切り替えたほうがよいという、利便性を追求した考えはないのです。
それで皮膚科医や小児科医や精神科医、そしてそれらの医師にかかっている患者と家族は「オンライン診療は結局使いづらい」と感じてしまったのです。
これが2018年4月以降オンライン診療の普及が減速した背景です。
そのほかの「使いにくさ」
オンライン診療システム「クリニクス」を運営しているメドレー社の幹部は、医療現場(臨床現場)の実態を踏まえ、オンライン診療の対象疾患を再検討する必要があると述べています。
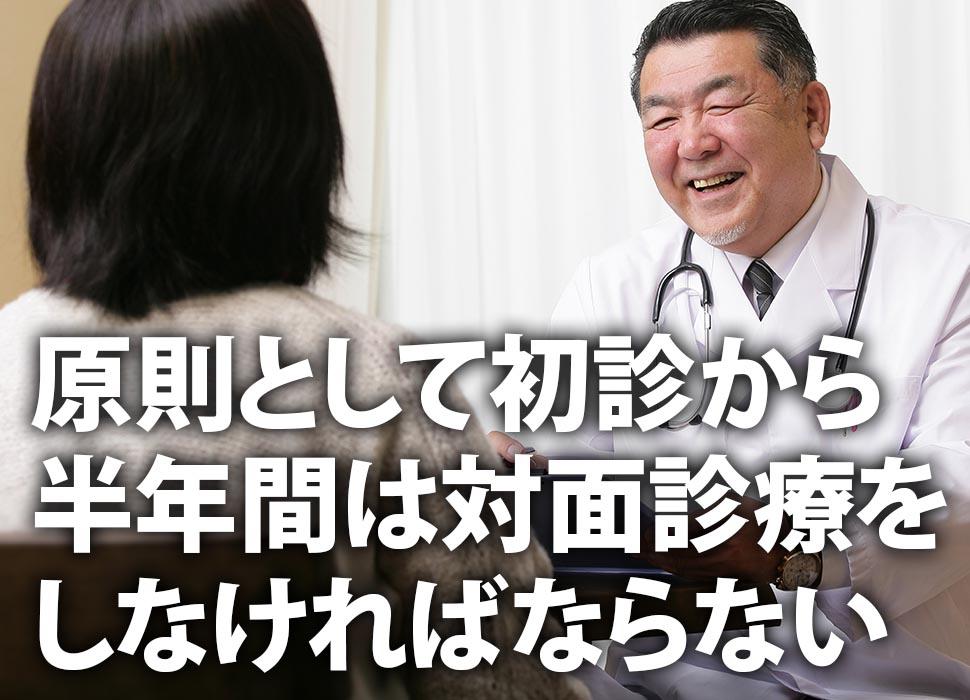
また、例外はありますが、原則として初診から半年間は対面診療をしなければならないルールも、オンライン診療を使いづらくしています。
さらに、対面診療での治療が半年経過すればオンライン診療をスタートできるわけですが、その後も3カ月に1回は対面診療を行わなければならないのです。
そもそもの話、半年が経過する前に治療を終えてしまう場合においては、この医療機関でオンライン診療を受ける事は一切ないのです。
また、オンライン診療を行えるのは、対象の患者が急変したときに30分以内に対面診療が可能な医師に限られます。
すなわち、神奈川県の患者が東京の医師のオンライン診療を受けることはできない、ということです。
まとめ~会社員は利用しづらい
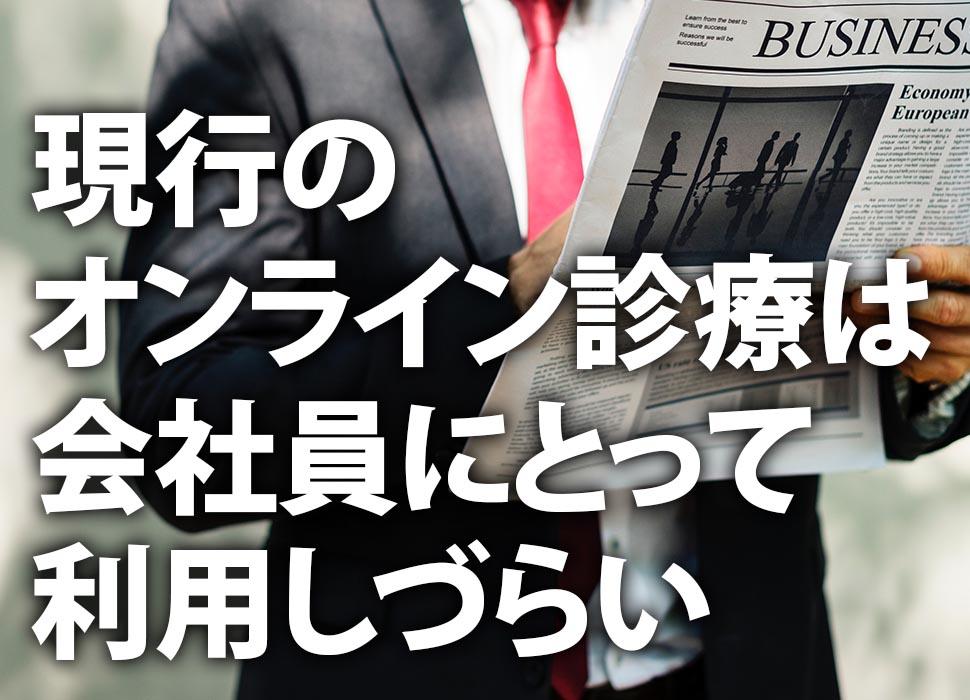
日本遠隔医療学会は、長年、オンライン診療(遠隔診療)の普及拡大に尽力してきた団体です。
その幹部が「オンライン診療が公的医療保険の対象になったことで、かえって後退してしまった部分もある」と述べています。
皮膚科、小児科、精神科のみならず、耳鼻科、眼科の病気も対象外だからです。
これらの診療科の治療は、日々元気に働いている会社員も必要とします。
上記の診療科がオンライン診療の対象となれば、仕事に支障が出ない範囲で治療を受けることができるのですが、本記事執筆時点の2018年10月現在は難しい状況ですので、今後の関係団体や厚生労働省等の話し合いを重ねて頂き、これらの事が改善されて使いやすくなってくれる事を願うほかなさそうです。
料金設定も「予約料500円+お薬の送料一律500円+お薬代」のみとなっております。
厚生労働省の告知に基づき、当クリニックでの初診は来院で受診して頂いた上で、
再診時よりオンライン診療による受診が可能となります。
この記事を読んだ方は他にこんな記事も読んでいます
-
【2018年版 動き出すオンライン診療3】在宅のお看取りで医師の負担が大幅減少
2018年6月22日
※本記事はシリーズとなっておりますので前記事からの閲覧をおすすめ致します。前々記事『【2018年版 動き出すオンライン診療1】新制度はこうなる』はこちらからご覧ください。前記事『【201...
詳しく見る >
-
オンライン診療(遠隔診療)の学会って?そもそも何をもって学会と言うのか
2018年6月13日
一般の人が、医療や病気についてインターネットなどで調べていくと、「学会」という単語と出会うと思います。 もしくは「学会が言っているのだから、間違いなさそうだ」と思ったことがあるでしょう。 ...
詳しく見る >
-
医師も患者も助ける病理診断の遠隔化
2018年3月12日
医療はすさまじいスピードで進化していて、これまで治らなかった病気が簡単に治るようになることも珍しくありません。そのような画期的な出来事はニュースでも報じられ、一般の人たちも「医療は確実に進化し...
詳しく見る >
-
オンライン診療は「こう変わる」厚労省が見直しに着手
2019年4月9日
厚生労働省が2019年1月、オンライン診療(遠隔診療)の在り方を見直す作業に入りました。 オンライン診療は2018年4月に公的医療保険の対象になり本格的にスタートしましたが、依然として規制が...
詳しく見る >
-
あのYahoo!も本格参戦① かんたん医療相談がスタート
2017年11月21日
インターネット検索でおなじみのYahoo!が2016年10月に始めたかんたん医療相談は、24時間いつでも医師に相談できるネットサービスです。医師に相談できるサイトは他社も出していますが、Yah...
詳しく見る >
-
オンライン診療(遠隔診療)の保険診療と自由診療
2018年3月1日
日本の医療では、原則すべての国民がなんらかの公的医療保険に加入しています。これを皆保険といい、医療保険に入っていると病院で支払う治療費の自己負担額は1~3割で済みます。もうひとつ自由診療という...
詳しく見る >