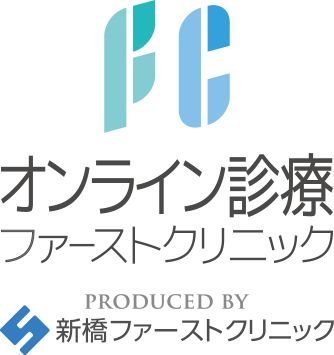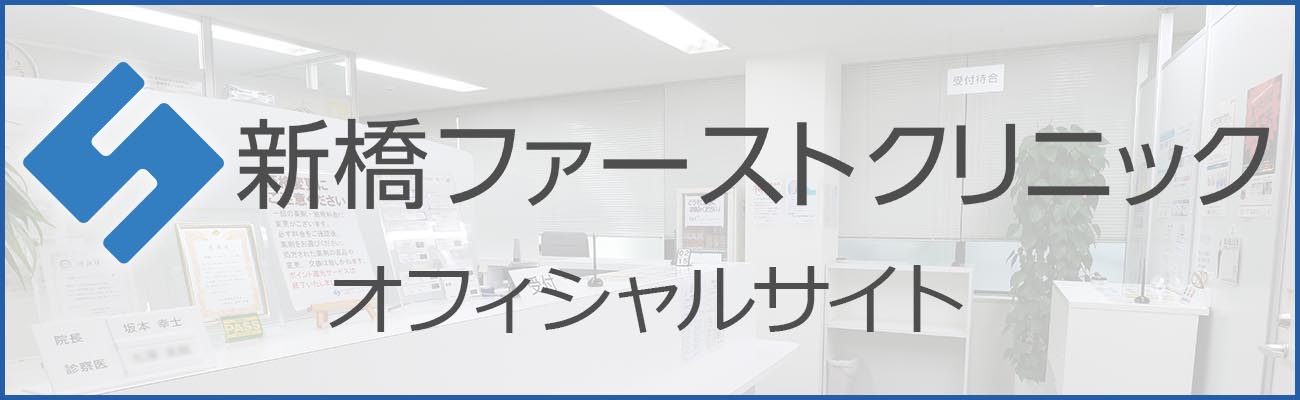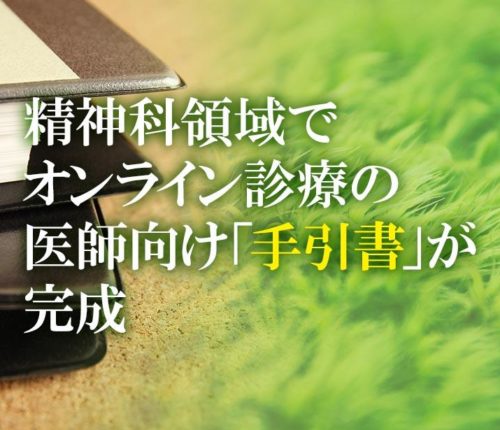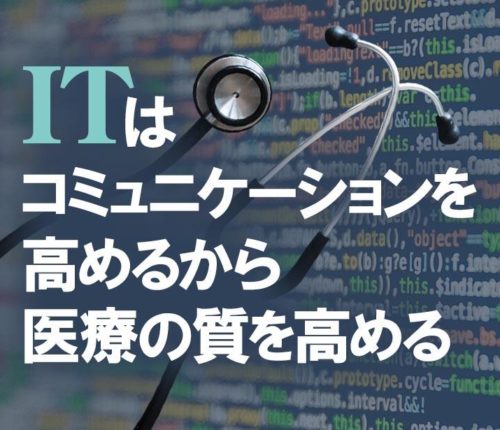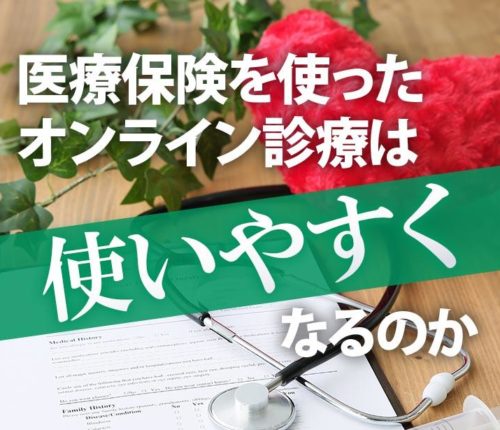Telemedicine Report
記事リリース日:2019年5月22日 / 最終更新日:2019年5月22日
【基礎からわかるオンライン診療】
治療の対象外になっている病気とは
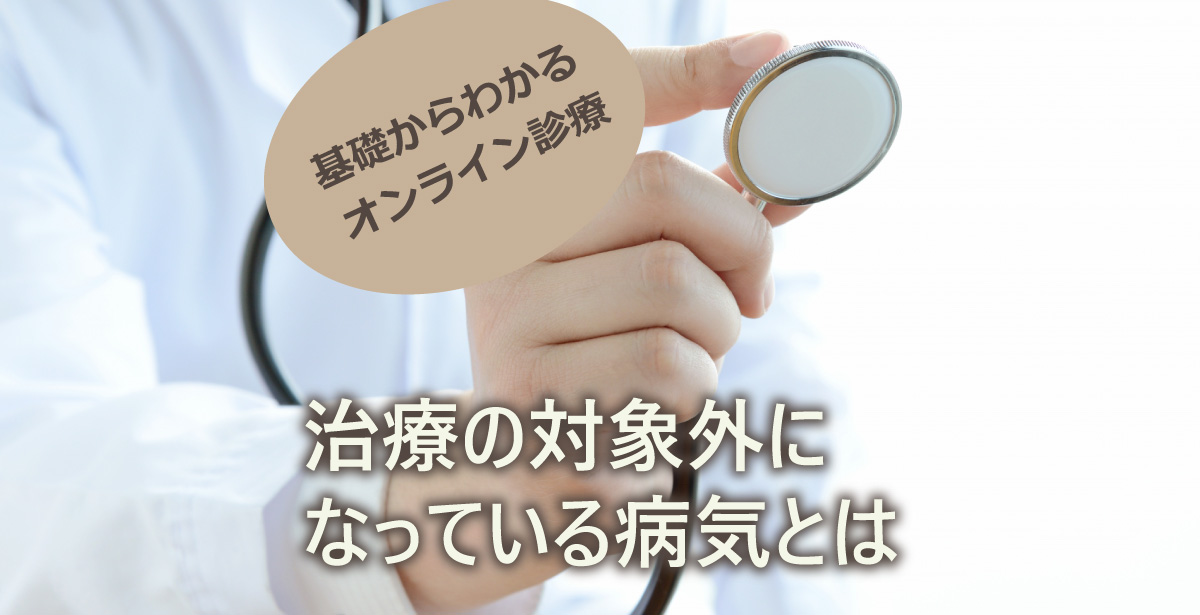
患者がスマートフォンで医師の診察を受けることができるオンライン診療は、まさに「未来の医療が実現した」といえるでしょう。
しかしオンライン診療は、すべての患者が使えるわけではありません。
ある病気の患者は、オンライン診療のサービスを受けられないのです。
厚生労働省が「オンライン診療はこの病気の治療にしか使ってはならない」と決めているからです。
そのため、「オンライン診療は使いにくい」という声が、医師や患者から漏れ始めています。
オンライン診療はなぜ、すべての病気の治療に使えるわけではないのでしょうか。
目次
シリーズ「基礎からわかるオンライン診療」について
オンライン診療(遠隔診療)が2018年4月から公的医療保険の対象となり、未来の医療が身近な医療になりました。
しかし、まったく新しい医療のため「よくわからない」と感じている人も多く存在します。
そこで、シリーズ「基礎からわかるオンライン診療」では、医療に詳しくない方でも理解できるように、オンライン診療に関する基本的な情報をなるべく専門用語を使わず、平易な言葉で解説していきます。
オンライン診療は「この病気」の治療にしか使えない

公的医療保険制度には、「この治療方法はこの病気の治療にしか使えない」というルールがあります。
それは、ある治療法は特定の病気を治すために開発されたものだからです。
もし仮に、その治療法で別の病気が治ったとしても、それは単なる偶然かもしれません。
単なる偶然の治療法を公的医療保険の対象とするわけにはいかないので、「この治療方法はこの病気の治療にしか使えない」というルールは厳格に運用されています。
それでは、オンライン診療は「どの病気」にしか使えないのでしょうか。
オンライン診療は10分類に含まれる病気にしか使えない
オンライン診療が使える病気は、次の10の分類に含まれる病気だけです(※1)。
- (1)「B000」特定疾患療養管理料の算定対象となる病気
- (2)「B001」の「5」小児科療養指導料の算定対象となる病気
- (3)「B001」の「6」てんかん指導料の算定対象となる病気
- (4)「B001」の「7」難病外来指導管理料の算定対象となる病気
- (5)「B00」の「27」糖尿病透析予防指導管理料の算定対象となる病気
- (6)「B001-2-9」地域包括診療料の算定対象となる病気
- (7)「B001-2-10」認知症地域包括診療料の算定対象となる病気
- (8)「B001-3」生活習慣病管理料の算定対象となる病気
- (9)「C002」在宅時医学総合管理料の算定対象となる病気
- (10)「I010」精神科在宅患者支援管理料の算定対象となる病気
この10分類は「専門用語」なので、具体的な病名を紹介します。
以下のとおりです。
- 結核、悪性新生物(がん)、糖尿病、高血圧性疾患、心不全、喘息、胃潰瘍、胃炎、慢性ウイルス肝炎など32の病気(以上、上記の1)(※2)
- 脳性麻痺、先天性心疾患、ネフローゼ症候群、ダウン症等の染色体異常などの病気(以上、上記の2)(※3)
- てんかん(上記の3)
- 球脊髄性筋萎縮症や筋萎縮性側索硬化症など難病法に規定する指定難病331種の病気(以上、上記の4)(※4)
- 脂質異常症や認知症など(以上、上記の6)
- 統合失調症、妄想性障害、気分(感情)障害、重度認知症など(以上、上記の10)(※5)
これらの病気の患者は、オンライン診療による治療を受けることができます。
このように並べると「多くの病気が含まれている」と感じるかもしれませんが、実は意外な病気がこのなかに含まれていないのです。
- ※1:http://shirobon.net/30/ika_1_1_2/a003.html
- ※2:https://medical.mt-pharma.co.jp/support/sh-manual/pdf_2018/sh_03.pdf
- ※3:http://shirobon.net/30/ika_2_1_b001/b001_05.html
- ※4:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html
- ※5:https://medical.mt-pharma.co.jp/support/sh-manual/pdf_2018/sh_all.pdf
この病気の治療にはオンライン診療は使えない

「素人考え」ではオンライン診療に向いていそうなのに、実際はオンライン診療の対象から外れている病気があります。
そして「素人考え」が医師の考えと一致することは珍しくありません。
現場の医師も「この病気こそオンライン診療の治療対象にしたほうがいいのに」と考えていることが多いのです。
それを紹介します。
皮膚の病気はオンライン診療の治療対象ではない
アトピー性皮膚炎などの皮膚科の病気は、オンライン診療の治療対象になっていません。
皮膚科の医師のなかには、「アトピーはオンライン診療に向いている」と考えている人もいて、それは皮膚の病気の治療には次のような特徴があるからです。
- ・症状が固定すると経過観察になることがある
- ・同じ薬を継続して使うことが多い
- ・患者がスマホのカメラで皮膚を撮影して送信すれば医師が状態を観察できる
オンライン診療は経過観察と継続的な薬の処方を必要とする病気に向いているといえます。
なぜなら、経過観察だけならわざわざ患者に来院してもらわなくても、テレビ電話方式のオンライン診療で対応できるからです。
また、同じ薬を継続的に使うなら、これもわざわざ患者に来院してもらわなくてもよさそうです。
医師にも患者にも「皮膚の病気はオンライン診療で治療できるようにしたほうがよい」という意見がある一方で、皮膚科の医師たちで構成する日本皮膚科学会と日本臨床皮膚科医会は、まったく逆の見解を示しています。
この2つの学会は2018年11月に「皮膚科診療における遠隔医療の位置付け」という文章で、皮膚の病気の治療はオンライン診療に向いていない、との見解を示しています。
この2つの学会がオンライン診療による治療に反対する理由は、水虫の治療がオンライン診療では難しいと考えるからです。
皮膚科クリニックの患者の10%は水虫治療です。
水虫の診断には、皮膚表面や爪の内側の水虫菌(糸状菌)を顕微鏡で確認する必要があり、それはオンライン診療ではできません。
また皮膚腫瘍(いわゆる皮膚がん)や炎症性の皮膚の病気は、医師が患者の皮膚に直接触れて硬さや弾力性を調べなければなりません。
当然ですが、このような触診(医師が患者に触る診療)はオンライン診療では不可能です。
こうしたことからこの2つの学会は、オンライン診療は皮膚の病気の治療において誤診や重大な病気を見落とす危険がある、と考えているわけです(※6)。
それでも現場の皮膚科の医師のなかには「通院が面倒で治療を中断する患者さんもいるので、ぜひ皮膚科もオンライン診療の対象にしてほしい」といった意見が根強く存在します(※7)。
2つの学会の明確な声明が存在するものの、皮膚科の専門家たちが今後さらに議論を深めていくことを期待したいところです。
うつ病はオンライン診療の治療対象ではない

うつ病も、オンライン診療の治療対象から外れていますが、一部の精神科の医師は「うつ病の治療はオンライン診療に向いている」と話しています(※8)。
それは、うつ病の治療は長期化する一方で、症状が安定すれば経過観察と薬の処方だけで済むこともあるからです(※9)。
もちろん、重度のうつ病患者は自殺を図ることもあるので、オンライン診療“だけ”で治療することはできないでしょう。
しかし、うつ病の患者が「治療は継続したいけど、通院のためとはいえ外出したくない」と考えたとき、オンライン診療という選択肢があるかないかは大きな違いとなるでしょう。
つまりオンライン診療なら、「外に出ないでいいのなら治療を継続したい」と考えるうつ病患者を医療機関につなぎ止めることができるかもしれないのです。
そして野村総合研究所によると、実際にオンライン診療を実施している精神科医は、うつ病の治療にオンライン診療を使っています。
同研究所が医師たちに「オンライン診療を使っている病名」を尋ねたところ、うつ病や適応障害などを含む精神疾患を挙げた医師は17.3%に及びました(※10)。
これは決して少ない人数ではありません。
これらの医師たちが公的医療保険を使っているかどうかは不明ですが、少なからぬ精神科医が、うつ病を含む精神疾患の治療におけるオンライン診療の有用性を実感しているのは事実のようです。
まとめ~患者のほうがITとネットの可能性を信じている?
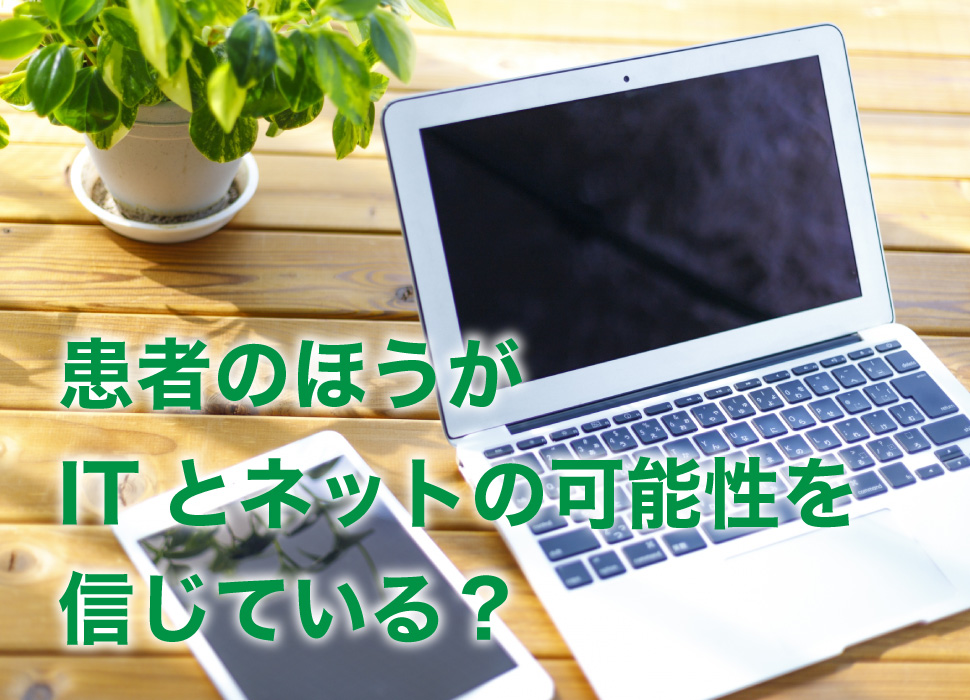
患者にとっては、わざわざ医療機関に行かなくてよいオンライン診療はとてもありがたい医療です。
しかし医療のプロである医師たちは、少しでもリスクがある医療は避けたいと考えます。
特に、安易にオンライン診療を使うことを警戒する医師は多いようです。
患者と医師の間にこのようなギャップが生じるのは当然のことであり、そしてギャップがあるからこそ安全な医療が行われている、ともいえます。
しかしオンライン診療はITとインターネットを使った医療であり、そして医師たちよりITとインターネットに詳しい患者はたくさんいます。
オンライン診療で治療できる病気を増やしてほしいと考えている患者や一般の人や医師は、ITとインターネットの力を信じている人なのかもしれません。
料金設定も「予約料500円+お薬の送料一律500円+お薬代」のみとなっております。
厚生労働省の告知に基づき、当クリニックでの初診は来院で受診して頂いた上で、
再診時よりオンライン診療による受診が可能となります。
この記事を読んだ方は他にこんな記事も読んでいます
-
精神科領域でオンライン診療の医師向け「手引書」が完成
2019年2月14日
オンライン診療(遠隔診療)を行っているクリニックの医師にとって、待ち望んでいたものがようやく完成しました。 国内初の、オンライン診療を行っている医師向け「手引書」が、慶応義塾大学医学部などに...
詳しく見る >
-
ITはコミュニケーションを高めるから医療の質を高める
2018年10月12日
「日本の医療はもっとIT化したほうがよい」と言ったら、驚く人がいるのではないでしょうか。 「日本の医療は世界最高水準だから、十分IT化されているはずだ」と思った方は、考えをあらためたほうがよ...
詳しく見る >
-
オンライン診療(遠隔診療)は被災地支援にマッチする
2018年11月19日
地震や台風の被災地では普段より多くの医療が必要になるのに、医療が壊れるという、二重苦に襲われます。 住民たちは、最も医療を必要とするタイミングで、“近くの医療”を失う状況に恐怖すら感じる...
詳しく見る >
-
医師も患者も助ける病理診断の遠隔化
2018年3月12日
医療はすさまじいスピードで進化していて、これまで治らなかった病気が簡単に治るようになることも珍しくありません。そのような画期的な出来事はニュースでも報じられ、一般の人たちも「医療は確実に進化し...
詳しく見る >
-
人工知能はどうやって人を治すのか【テクノロジーが医療を変える】
2018年7月12日
自分が病気をして病院に行ったとします。受付で「医師による診察を希望しますか。それとも人工知能(AI)による診察を希望しますか」と聞かれたらどちらを選択するでしょうか。 恐らく多くの人は、「A...
詳しく見る >
-
医療保険を使ったオンライン診療は“使いやすく”なるのか
2019年1月17日
2018年4月1日は、日本のオンライン診療(遠隔診療)の歴史上、よい記念日でもありますが、よくない記念日としても記録されるでしょう。 よい記念日になるのは、このときからオンライン診療が本...
詳しく見る >