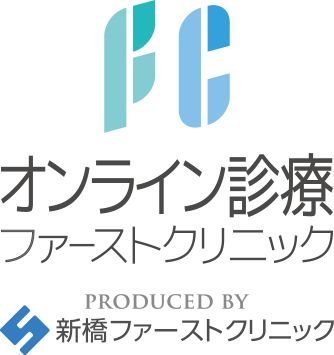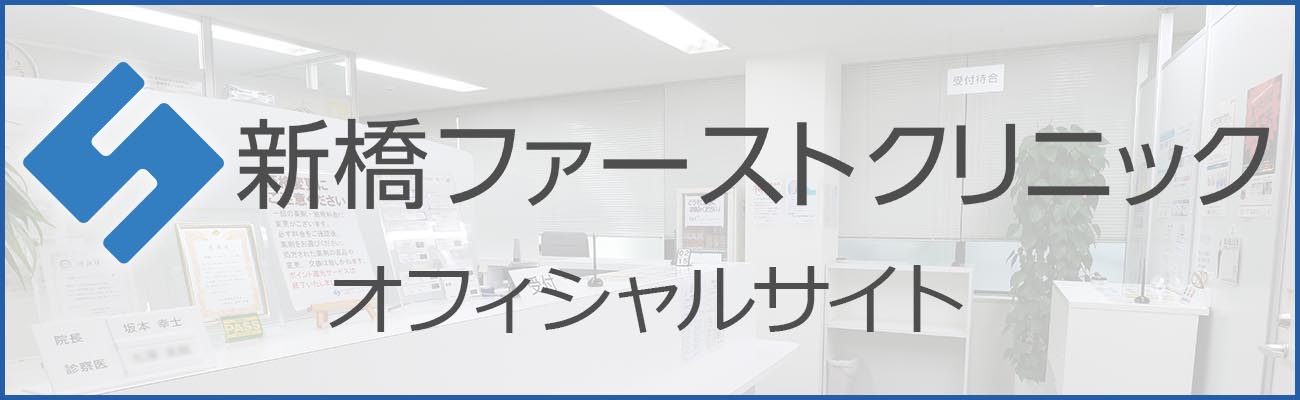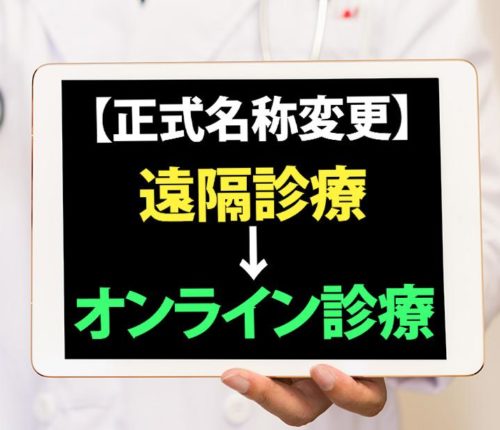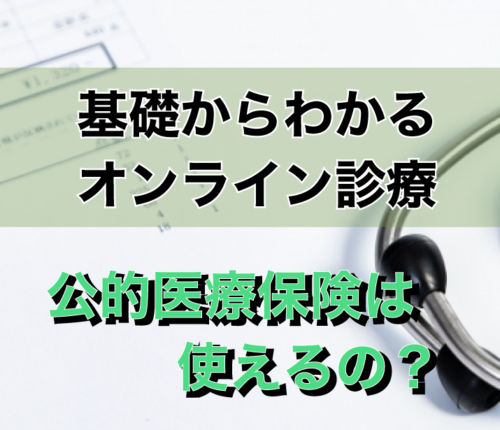- 2025/12/03:クリニクスによるオンライン診療は終了いたしました
- 2025/02/12:LINEでオンライン診療を受けられるようになりました(詳しくはこちら)

Telemedicine Report
記事リリース日:2019年6月26日 / 最終更新日:2019年6月26日
オンライン診療の次に来る
「リモートケア」とは
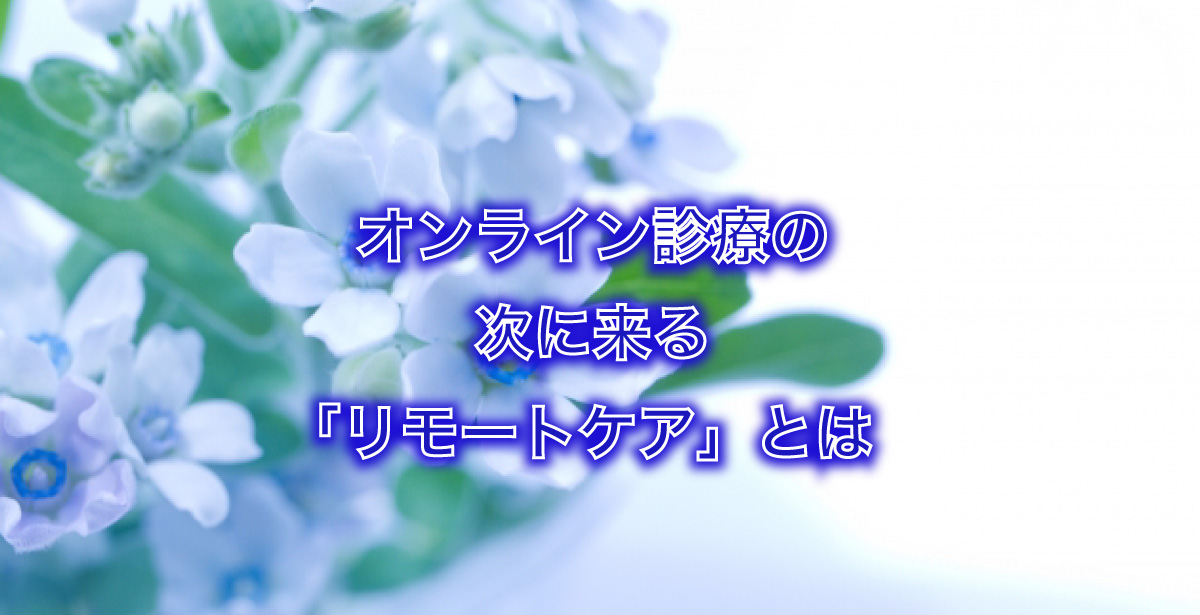
オンライン診療とは、患者さんと医師をインターネットの電話会議システムでつなげて行う診療のことです。医師はパソコンを使い、患者さんはスマートフォンを使います。
オンライン診療はITをふんだんに使ったまったく新しい医療で、2018年4月に厚生労働省が正式に公的医療保険の対象として認可しました。
したがってオンライン診療は「できたてほやほや」の医療なのですが、すでにオンライン診療の次の構想が誕生しています。
リモートケアです。
リモートとは「遠隔」という意味です。ケアとは、医療や介護やその他のお世話のことです。しかしリモートケアは、単なる遠隔操作による医療や介護やその他のお世話、ではありません。
オンライン診療ですら十分革新的なのに、それをさらに進化したリモートケアとはどのようなものなのでしょうか。
目次
多喜義彦氏が考えるリモートケアとは
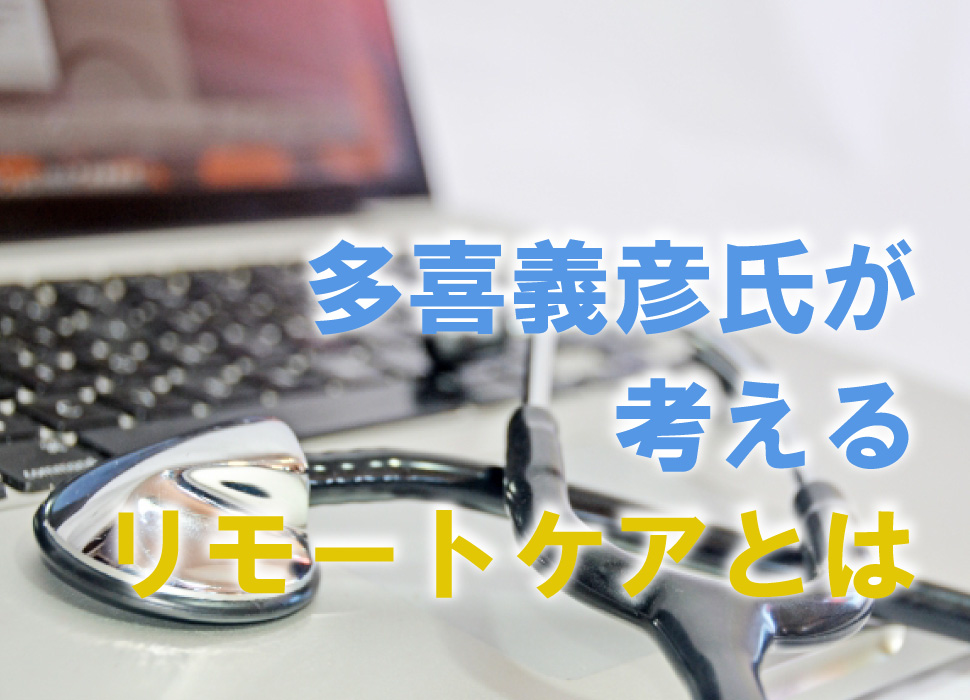
リモートケアの提唱者の1人に、多喜義彦氏という方がいます。多喜氏の考えるリモートケアとは、およそ次のような内容を含んでいます。
- ケアする人(医師や看護師や介護職員など)とケアされる人(患者さん、高齢者など)が遠隔地にいる
- 双方がスマホやタブレットなどの専用端末を使う
- オンライン診療を含む
- 専用端末は次のことにも使う
【買い物、ケータリング、行政サービスの告知、情報配信、その他、患者さんや高齢者などの身の回りのすべての世話】
多喜氏とは
オンラインケアの詳細を解説する前に、多喜氏について紹介します。 多喜義彦氏は、システム・インテグレーション株式会社(本社・東京都千代田区)の社長です。同社は企業のシステムなどをつくっている会社で、現在40数社の技術顧問をしているそうです。
多喜氏にはビジネスパーソンの顔の他に「公の顔」を持っています。例えば、東北大学や金沢大学や九州工業大学などの客員教授を歴任しています。宇宙航空研究開発機構(JAXA)の知財アドバイザーを務めたこともあります。
また、日本経済新聞系列で、医療やITやビジネスなどに関する雑誌を多数出版している日経BPにおいて、リアル開発会議プロデューサーという肩書を持っています。
多喜氏は「開発の鉄人」と呼ばれています。
リモートケアがなぜ「今」必要なのか

2019年4月26日付けの日経XTECの記事「遠隔診療、オンライン診療の次は『リモートケア』」で多喜氏は、2040年に国民の4分の1が75歳以上になる日本で、リモートケアは「絶対に必要なものであると確証している」と述べています(*)。
*:https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00028/00024/?P=1
多喜氏は、2018年4月に本格稼働したばかりのオンライン診療は、高齢者が増えたことで医療のコストが膨張したため、医療を効率化するために生まれた、と考えています。
実際、厚生労働省もオンライン診療の導入において、医療の効率化を検討しています(*)。
オンライン診療の進化形であるリモートケアは、医療だけでなく介護やその他の社会的なケアを効率化させる、というわけです。
セキュリティ技術が確立されてきたから
では、多喜氏はなぜ、オンライン診療が始まったばかりの「今」、次のステップであるリモートケアを提唱しているのでしょうか。つまり、日本の超高齢社会問題は、10年以上前から議論されていたのに、なぜオンライン診療の本格稼働直後のこのタイミングだったのでしょうか。
多喜氏は、リモートケアを社会に普及するには、情報セキュリティを強化する必要がある、と考えています。オンライン診療ですら、とても重要な医療情報がインターネット上を飛び交っています。リモートケアになれば、医療情報すら重要情報群のひとつにすぎなくなります。
患者さんや高齢者の「人生そのもの」がインターネットやパソコンやスマホでやり取りすることになるのです。
したがってリモートケアでは、患者さんと医師が完全に特定されなければなりません。そのためには、指紋や顔などで本人を特定する生体認証システムが必要になります。
こうしたより高度な技術が「今」になってようやく成熟してきたので、リモートケアを考えられるようになったのです。
富士通のリモートケアとは
多喜氏以外にもリモートケアを考えている人たちがいます。例えば富士通は、介護施設で使うリモートケアを開発しました。
それは「居住者の見守りソリューション リモートモニタリングサービス」(以下、見守りリモートサービス)といい、介護施設の居室で高齢者が転倒した場合などに、介護スタッフに迅速かく的確に伝える仕組みです。
介護職員の負担を減らしながら高齢者の転倒を素早く検知

富士通の見守りリモートサービスは、介護施設内の高齢者が、自分の部屋のなかで転倒し、起き上がれない状態を想定しています。
介護が必要な高齢者でも、足や腰の間接や筋肉が動けば、立ち上がって歩きたくなるものです。しかし一度転倒してしまうと、自力で起き上がれないことがあります。
個室でそのような事態が発生すれば、転倒した高齢者は、介護職員の次の巡回まで倒れたままになってしまいます。これは命の危険につながってしまいます。
見守りリモートサービスで使われているのは、特殊な音響センサーです。最も単純な音響センサーは、音が鳴らないはずの場所に設置して、音が鳴ったらアラームで監視員に知らせるものです。
見守りリモートサービスで使われている音響センサーは、高齢者が転倒したときの異常な音だけでなく、例えば一定時間まったく音がしなくなったときも介護職員に知らせます。さらに室内の温度や湿度が異常数値を示したときも知らせます。
介護職員は専用のアプリをダウンロードしたスマホを携行し、見守りリモートサービスの通知を受けたら対象の高齢者の個室に駆けつけるわけです。
リモートケアがとても必要な介護施設の特殊事情
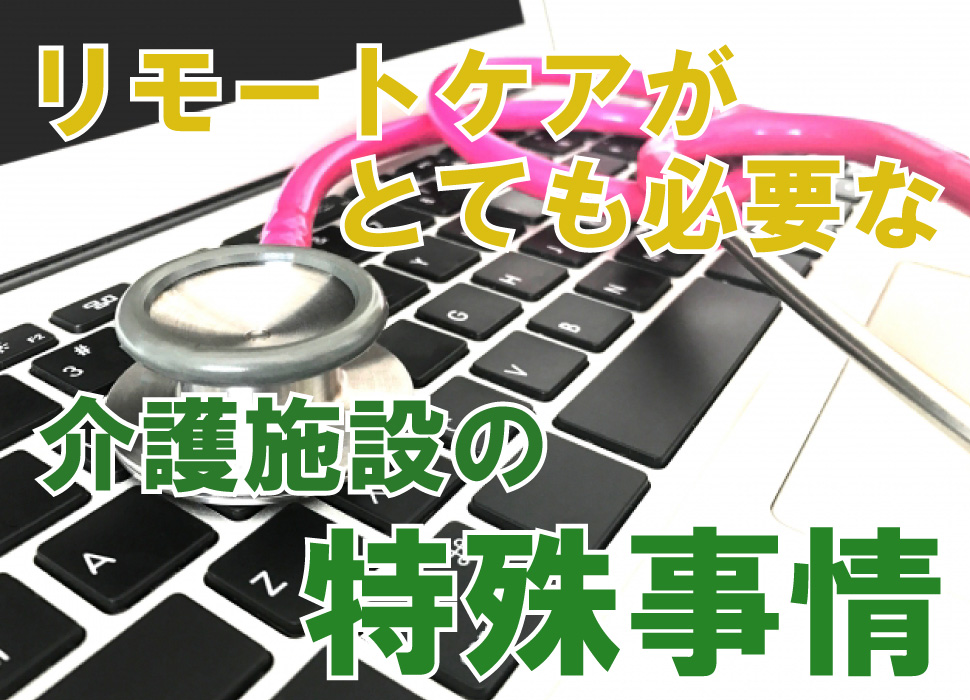
介護業界の人手不足は深刻化していて社会問題になっています。介護の人手不足の最も大きな要因は高齢者の増加と労働人口の減少ですが、別の要因もあります。それは、介護の仕事に就きたい人が少ないことです。
介護の仕事が不人気なのは、重労働の割に給料が高くないこともありますが、「仕事が大変」という事情もあります。
かつての介護施設では、複数の高齢者を大広間に入れていました。例えば1室に6人の高齢者がいれば、介護職員は一気に6人分の介護をすることができます。6人分の見守りも1回で済みます。
ところが高齢者のプライバシーと人権を守るために、介護施設の個室化が進みました。これは「とてもよいこと」です。介護が必要な高齢者であっても、羞恥心はあります。大部屋の多くの他人がいるなかで、カーテンで仕切られているとはいえ、オムツ交換をされるのは嫌なものです。屈辱に感じ、生きる気力をなくす高齢者もいるでしょう。
介護施設の個室化の流れは当然なのですが、その代わり、介護職員の仕事が増え、なおかつ濃密になりました。 夜間の見守りなら、介護職員は個室のドアをノックしてから入室し、寝ている様子をみて無事を確認し、部屋を出て次の部屋に行かなければなりません。 6人部屋であれば6人分の見守りは1回で済みましたが、個室になると6回行わなければなりません。
介護職員を増やせば対応できますが、介護保険制度から給付される介護報酬は、公的医療保険制度から給付される診療報酬よりはるかに低額なので、介護施設の運営者は人件費が増える増員を行えません。 それで介護職員の労働が濃密化して離職者が増え、残った介護職員の負担がさらに増え、さらに離職者が増えるという悪循環を起こしているのです。
見守りリモートサービスを使えば、介護職員による無駄な巡回を減らすことができるので、介護職員は床ずれ防止のための寝返り補助(体位交換)や定期的なオムツ交換や緊急対応に専念できます。 すなわち、リモートケアを導入することで、1)介護職員の負担軽減と2)高齢者へのケアの充実と3)介護事業者の人件費削減と4)人材確保の4つのメリットを享受できるかもしれないのです。
見守りリモートサービスは介護施設だけでなく、クリニックや訪問看護ステーションと患者宅をつなぐこともできます。また、セキュリティ会社と高齢者宅をつなぐこともできます。 リモートケアのひとつの手段として、活躍の場はさらに広がりそうです。
まとめ~今そこにある課題と利便性
「オンライン診療が本格稼働したばかりなのに、もう次のリモートケアを考えなければならないのか」と思うかもしれません。しかし、リモートケアは、オンライン診療の進化版と考えることができるので、まったく新しいものを一から導入するわけではありません。
そしてリモートケアは、患者さんも高齢者もその家族も医師も看護師も介護職員も、メリットを受けることができます。4分の1の75歳以上の人たちを、4分の3の75歳未満の人たちで支えるには、ITやインターネットなどの最新技術が欠かせません。
料金設定も「予約料500円+お薬の送料一律500円+お薬代」のみとなっております。
厚生労働省の告知に基づき、当クリニックでの初診は来院で受診して頂いた上で、
再診時よりオンライン診療による受診が可能となります。
この記事を読んだ方は他にこんな記事も読んでいます
-
オンライン診療(遠隔診療)推進には東日本大震災が関係していた
2017年10月10日
必要は発明の母、と言いますが、医療が最も深刻に必要とされるのは、災害に見舞われた場所です。災害をきっかけに新しい医療が生まれることがあるのです。現代医療にとって電気は不可欠なインフラですが、被...
詳しく見る >
-
保険診療でなくても画期的「禁煙外来」で完全オンライン診療(遠隔診療)が可能に
2017年10月13日
厚生労働省はこれまで、医療機関がオンライン診療(遠隔診療)を行う場合、「初診だけは直接の対面診療をしなければならない」という立場を貫いてきました。 ところが同省は201...
詳しく見る >
-
ED治療・AGA治療はオンライン診療(遠隔診療)にマッチしそう
2018年1月31日
当クリニックを含め、オンライン診療(遠隔診療)を導入しているクリニックのホームページを閲覧すると、勃起不全(ED)と男性型脱毛症(AGA)の治療を手掛けるところが散見されます。EDとAGAは、...
詳しく見る >
-
ゲームで使うあのVRで不安障害を治療する
2019年3月28日
VRはバーチャルリアリティの略称で、仮想現実と訳されています。 VRはゲームで使われる技術で、大型のゴーグルのようなヘッドマウントディスプレイを頭に被り、360度の映像を楽しみます。 頭を...
詳しく見る >
-
遠隔診療の正式名称は「オンライン診療」に決定【医療の名は意外と重要】
2018年4月2日
昨今様々なメディアなどで話題となっている、スマホやパソコンなどの機器を用いて医師と患者が繋がって診療を受ける診療システムの一般的な通称である「遠隔診療」の名称が、2018年2月8日に正式名称と...
詳しく見る >
-
【基礎からわかるオンライン診療】公的医療保険は使えるの?
2019年6月7日
シリーズ「基礎からわかるオンライン診療」では、最近医療現場で使われるようになってきたオンライン診療について、患者さんや一般の方が「いまさら聞けない」と感じている基本的なことを、じっくり解説していま...
詳しく見る >