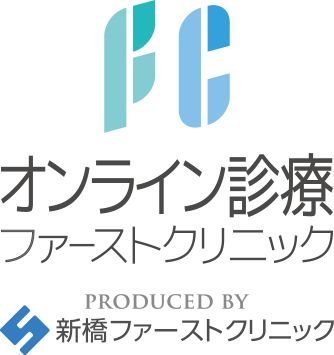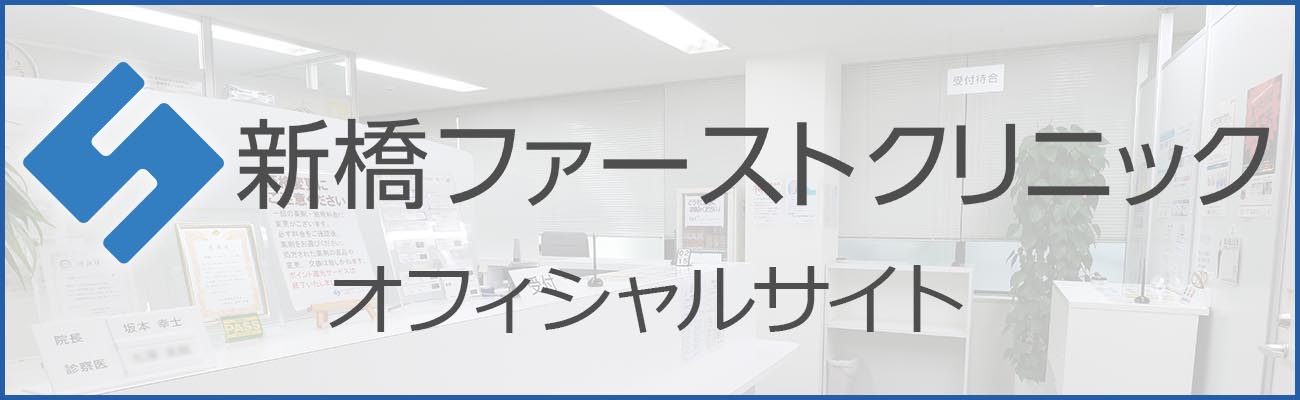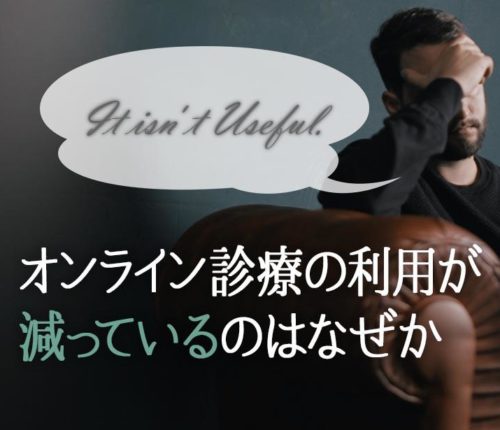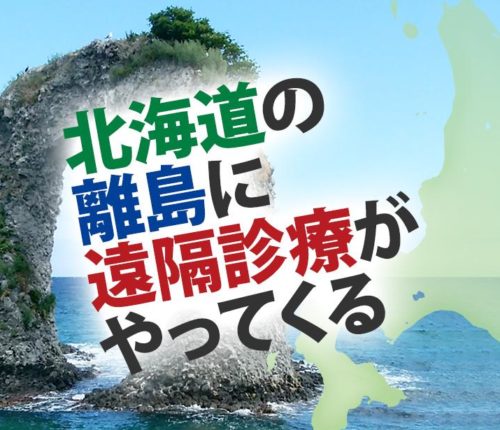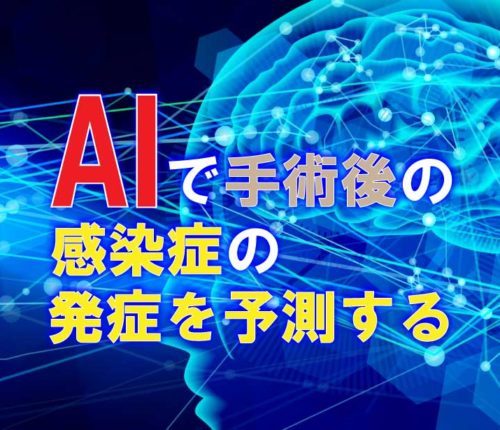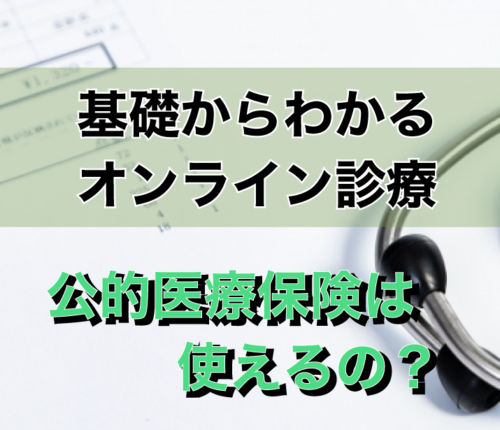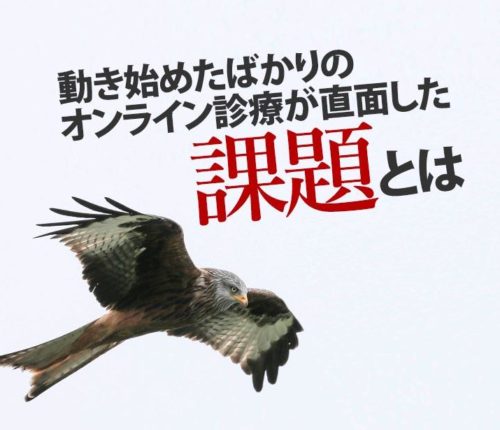- 2025/12/03:クリニクスによるオンライン診療は終了いたしました
- 2025/02/12:LINEでオンライン診療を受けられるようになりました(詳しくはこちら)

Telemedicine Report
記事リリース日:2017年10月13日 / 最終更新日:2019年1月18日
保険診療でなくても画期的
「禁煙外来」で完全オンライン診療(遠隔診療)が可能に

厚生労働省はこれまで、医療機関がオンライン診療(遠隔診療)を行う場合、「初診だけは直接の対面診療をしなければならない」という立場を貫いてきました。
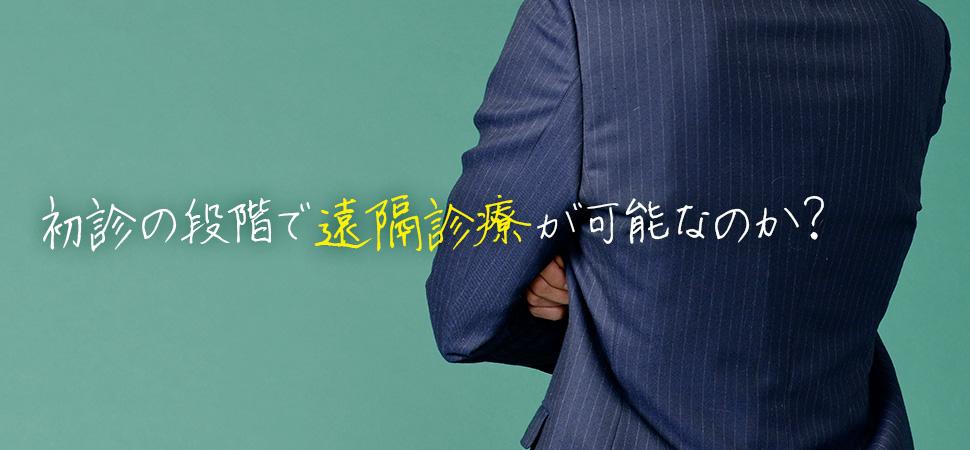
ところが同省は2017年7月に、「禁煙外来に限っては初診からオンライン診療(遠隔診療)を行ってもよい」と方針転換しました。
保険診療ではなく自由診療で行うことが条件なのですが、治療開始から終了まで医師と患者が一度も対面しない「完全オンライン診療」の実現はとても画期的なことなのです。
目次
少し条件は残るが画期的な方針転換
厚生労働省の方針転換は、全国の知事に宛てた事務連絡という形で公表されました。事務連絡の中の完全オンライン診療(遠隔診療)に関する部分のみを抜き出してみます。
“保険者が実施する禁煙外来については、定期的な健康診断・健康診査が行われていることを確認し、患者側の要請に基づき、患者側の利益と不利益を十分に勘案した上で、医師の判断により、直接の対面診療の必要性については柔軟に取り扱っても直ちに医師法第20条等に抵触するものではないこと。
なお、患者側の理由により診療が中断し、結果として遠隔診療のみで診療が実施された場合には、直接の対面診療が行われなくとも直ちに医師法第20条等に抵触するものではないこと。”
【引用元】 http://www.toyama.med.or.jp/wp/wp-content/uploads/2017/07/2017chi1_102.pdf
ご覧いただいて分かる通り、すんなりと禁煙外来であればオンライン診療(遠隔診療)を完全解禁するとは書かれていません。ポイントは3つです。
- ①完全オンライン診療(遠隔診療)は「保険者が実施する」「禁煙外来」に限る
- ②ただ保険診療は許可していない
- ③1度も医師と患者が対面しないで治療が中断しても医師法第20条に抵触しない
保険者と被保険者とは
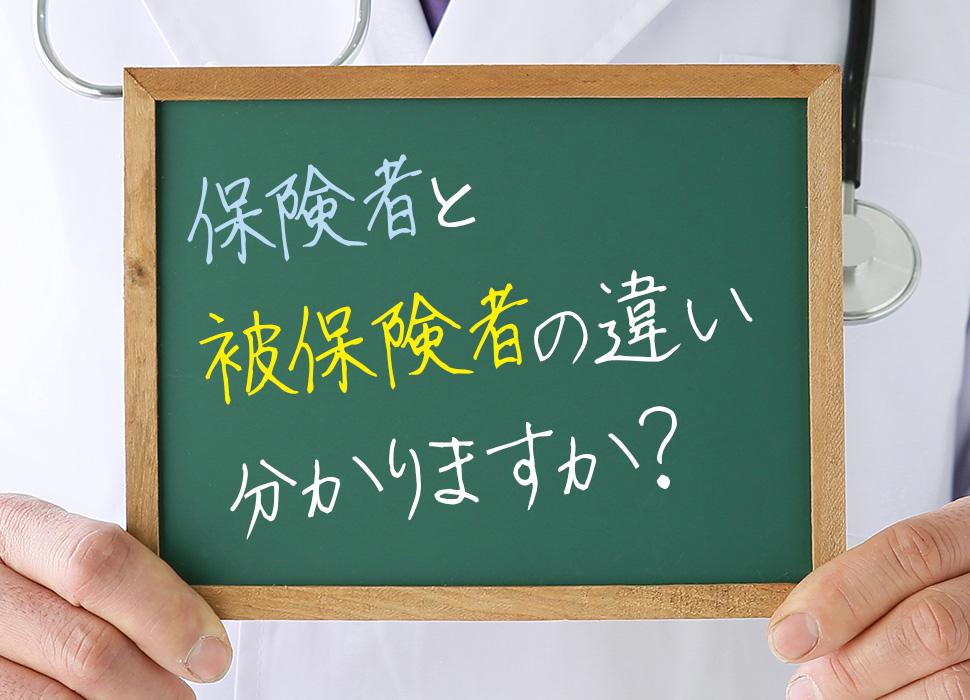
まず①の「保険者」について簡単に説明します。
公的医療保険(以下、医療保険)には、保険者と被保険者がいます。

被保険者は、働く人のことです。日本では、働く人は必ずいずれかの医療保険に加入しなければなりません。働く人が扶養している配偶者や子供や親なども、働く人が加入している医療保険を使えます。
保険者とは、被保険者から保険料を徴収し医療保険制度を運営している団体のことです。保険者となっている団体はたくさんあります。
保険者が実施するかどうかがカギ
保険者にはさまざまな種類があります。
大企業に勤めている人にとっては企業がつくる「健康保険組合」が保険者になります。
中小企業に勤めている人にとっては「協会けんぽ」が、公務員や教師にとっては「共済組合」が、国民健康保険に入っている自営業者にとっては市町村が、それぞれ保険者となります。
では、完全オンライン診療(遠隔診療)が許された保険者が実施する禁煙外来とは、どのような形態なのでしょうか。
これは保険者が医療機関に対し「うちの加入者の禁煙外来を行ってください」と委託することをいいます。
要するに厚生労働省は、保険者と医療機関が提携すれば、完全オンライン診療による禁煙外来を行ってもよいと言っているのです。
自由診療で行う
保険者が実施するオンライン診療(遠隔診療)による禁煙外来でも、保険診療にはなりません。保険診療とは、禁煙したい患者が保険証を示せば、年齢や所得などで変わってきますが多くても3割負担で済む診療形態のことです。
保険診療ではないということは、自由診療になるのですが、自由診療の治療費は医療機関が自由に定めることができ、その治療費は患者が全額自己負担します。
ただ専門家は、完全オンライン診療(遠隔診療)による禁煙外来では、患者が全額自己負担することは今後はなくなるだろうと見ています。保険者が治療費を全額負担するか、患者が一部だけ負担して残りは全額保険者が負担するだろう、と推測しています。
保険者が治療費を全額負担する形態も、自由診療の範疇に入ります。
保険者としては、医療保険制度に加入している被保険者が禁煙によって生活習慣病を発症しなければ治療費が浮き、医療保険財政にプラスの効果が出ます。よって禁煙外来の治療費を保険者が負担しても元は取れると考えることができるのです。
完全オンライン診療(遠隔診療)の禁煙外来が保険診療にならない理由
オンライン診療(遠隔診療)によらない禁煙外来、つまり直接の対面診療による禁煙外来は医療保険が適用されます。
なぜオンライン診療(遠隔診療)では医療保険が使えないのかというと、保険診療による禁煙外来を実施するには、様々な条件があるからです。
対面診療かつ保険診療で禁煙外来を行うためには、
- 1:受診希望者がニコチン依存テストで5点以上を取る
- 2:1日のタバコの本数の平均×これまでの喫煙年数=200以上
- 3:受診希望者がただちに禁煙を始めたいと思っている
- 4:受診希望者が禁煙治療を受けることを文書で同意している
つまり、ニコチン依存度が高い人しか、保険診療による禁煙外来を受けられないというわけです。
さらに、治療の途中で一酸化炭素測定器による息のチェックも行わなければなりません。
こうしたハードルの多さから、完全オンライン診療(遠隔診療)による禁煙外来を保険適用することは無理と判断されたようです。
しかしそれでも凄いことなのです。
日産、JAL、リクルート、野村証券、花王など18社が参入
先ほど、完全オンライン診療(遠隔診療)による禁煙外来を行えるのは、保険者と医療機関が提携したときのみ、という説明をしました。
早速動き出した保険者があります。

それは、日産自動車、日本航空、リクルート、野村証券、花王、コニカミノルタなど名だたる企業18社の健康保険組合(保険者)です。
この18社の健康保険組合はそれぞれ独立しているのですが、このオンライン診療(遠隔診療)禁煙外来のために連合体を組み、保険者が実施する禁煙外来を行うことを決めたのです。
この18社の健康保険組合の加入者は58万人にも達します。これだけの人に受診機会が与えられるのです。
18健康保険組合連合体は東京オリンピック・パラリンピックの2020年までに、加入者の3万人を禁煙させる、という目標も打ち立てました。
8週間に4回のオンライン診療(遠隔診療)、薬も自宅に届く
18社の健康保険組合連合体は2017年秋から実施する予定です。
オンライン診療(遠隔診療)禁煙外来の受診を希望する18社の社員は、登録を済ませたのち、医師からスマホやパソコンを使ってオンライン診療(遠隔診療)を受けます。受診する回数は8週間に4回程度です。
医師は禁煙補助薬が必要であると判断すると、患者の自宅や職場に宅配便で送ります。
8週間を過ぎてもサポートが必要な社員は、スタートから36週目までは、オンライン診療(遠隔診療)で保健師による禁煙継続の確認を受けることができます。
対面診療では64%が脱落。
オンライン診療(遠隔診療)だと10%のコストダウンも
厚生労働省によると、直接の対面診療による禁煙外来では64%の患者が途中で脱落しています。多忙な現代人にとっては、薬をもらいにいくためだけに通院することは、苦痛なはずです。
ところがオンライン診療(遠隔診療)であれば、通院の手間が100%省けます。しかも医療機関側にもメリットがあります。それは禁煙外来を直接の対面診療からオンライン診療(遠隔診療)に切り替えると10%ほどのコストが削減できるという調査結果があるのです。
医師もオンライン診療(遠隔診療)による禁煙外来を歓迎

禁煙治療に取り組んでいる医師たちも歓迎しています。
日本禁煙学会の理事で、産業医大の呼吸器内科教授は「遠隔外来で治療のチャンスが広がるのは良いこと。禁煙治療がうまくいかなかったときのフォローも必要」と毎日新聞の取材に答えています。
まとめ:オンライン診療(遠隔診療)の潜在能力を示す

子供からお年寄りまで、タバコが有害であることを知らない人はいないでしょう。国民の医療費が国の財政を圧迫していることも、広く知られているところです。 禁煙が進めば確実に病気は減り医療費も減ります。オンライン診療(遠隔診療)はその偉業を達成できる潜在能力を持っており禁煙外来はその第一歩として完全オンライン診療(遠隔診療)が認可されたのです。
料金設定も「予約料500円+お薬の送料一律500円+お薬代」のみとなっております。
厚生労働省の告知に基づき、当クリニックでの初診は来院で受診して頂いた上で、
再診時よりオンライン診療による受診が可能となります。
この記事を読んだ方は他にこんな記事も読んでいます
-
オンライン診療(遠隔診療)の利用が減っているのはなぜか
2018年11月28日
オンライン診療(遠隔診療)は2018年4月に、「公的医療保険の対象」になりました。 それまでは、スマホとネットを使ったオンライン診療は、電話による再診と同じ位置付けでしたが、それが「オンライ...
詳しく見る >
-
オンライン診療(遠隔診療)が首相官邸に到着した日
2018年1月12日
2017年5月10日はオンライン診療(遠隔診療)にとって記念すべき日になりました。その日に初めて、オンライン診療(遠隔診療)が首相官邸に届いたのです。安倍晋三首相の元にオンライン診療(遠隔診療...
詳しく見る >
-
北海道の離島にオンライン診療が届く日【遠隔診療が地方医療を救う】
2018年5月2日
もし北海道旅行を計画して、絶品のウニとアワビを食べたいと思ったら、奥尻島は必ず候補地の1つに加えておいてください。北海道の南西部の日本海に浮かぶこの島は、寒流と暖流に囲まれたおかげで良質な漁場...
詳しく見る >
-
AIで手術後の感染症の発症を予測する
2019年4月24日
AI(人工知能)が医療現場に進出しています。 AIといえば、囲碁の世界トッププロを破ったり天気予報の精度を上げたりと、人知を超える活躍をみせていますが、医療では人の命を救うことに貢献しています。...
詳しく見る >
-
【基礎からわかるオンライン診療】公的医療保険は使えるの?
2019年6月7日
シリーズ「基礎からわかるオンライン診療」では、最近医療現場で使われるようになってきたオンライン診療について、患者さんや一般の方が「いまさら聞けない」と感じている基本的なことを、じっくり解説していま...
詳しく見る >
-
動き始めたばかりのオンライン診療が直面した課題とは
2018年9月5日
医療保険制度上のオンライン診療(遠隔診療)が本格スタートから約3カ月が経過した2018年6月下旬、「オンライン診療カンファレンス」というイベントが開かれました。 このな...
詳しく見る >